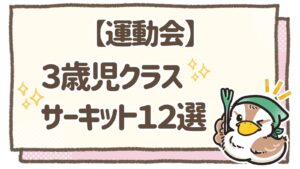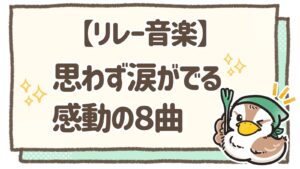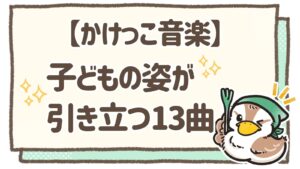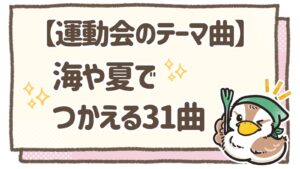かもねぎ
かもねぎこんなお悩みを解決します。
この記事を見ると保育園や幼稚園の運動会でつかう曲の選び方がわかります。



16回運動会を経験して、音楽選びのコツをまとめました。
- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 運動会を16回も経験


- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 運動会を16回も経験


記事の前半では「運動会の曲は保護者を意識する理由」を解説し、後半では「曲選びのポイント」や「選ぶ音楽ジャンルのメリット・デメリット」までまとめています。
「運動会の曲選びにいつも迷ってしまう」「どんな曲を選んだらいいかわからない」と思っている保育士さんや幼稚園の先生はぜひご覧ください。
“運動会の曲”は、競技のイメージを保護者に伝えるもの


音楽がいいと、保護者の運動会への満足度が50%アップする!
結論からいうと、
運動会の曲はその競技のイメージや雰囲気を伝えるものです。
ターゲットはずばり保護者!



もちろん子どもたちにとっても、競技中に流れる曲は重要です。
曲によってやる気になったり、わくわくしたりするでしょう。
ただ、子どもたちは身体を動かすことに集中していますし、大舞台に立って緊張もしています。音楽に聞き入る余裕はなく、なんとなく聞こえている感じではないでしょうか。
しかし、保護者はちがいます。
保護者は音楽を聞きながら、まるで映画やドラマを見るように、目の前の光景を見つめているのです。
それはいったいどういうことでしょうか?



みなさんがドラマを見る時を思い出してください。
盛り上がる音楽を聞くと、ワクワクしてぐっとドラマの世界にのめり込む。
緊張感のある音楽を聞くと、ドキドキして集中して見てしまう。
こんなことってありませんか?
これ、運動会の保護者も同じところがあると思います。
だから、かわいく見せたいところはかわいい曲にし、盛り上がってほしいところは盛り上がる曲にする。そうすることで、保護者は競技にぐっとのめり込み、運動会への満足感もぐーんと上がるのです!



もちろん、保護者の最大の喜びは“子どもたちのがんばっている姿”です。
運動会本番までのがんばりや競技内容などを事前に伝えることも大切ですよね。
ただ、BGMのないドラマが盛り上がりに欠けるのと同じで、曲のない運動会はありえません。
また、競技内容や子どもたちの姿と合わない音楽では、なんともいえない違和感が先にきてしまい、保護者は集中して見ることができません。
それでは保護者に満足感も生まれないですよね。
だから、私たちは「これぞ!」という曲を必死になって探すのです。



運動会のテーマやクラスの年齢、競技内容などにベストマッチな曲を探すことは、運動会を成功させるための大きな要素になります。
みんなが知っている曲には“特別な力”がある


一瞬にしてたくさんの人の気持ちが1つになり、いい雰囲気ができあがる!
たとえば、いまのお母さんやお父さんたちが知っている曲と言えば、嵐の“happiness”やSMAPの“世界に一つだけの花”、忍たま乱太郎の主題歌“勇気100%”などでしょうか。
お母さんやお父さんたち保護者が子どもの頃に聞いていた曲や、若い時に大好きだった音楽を流すと、「おっ!!」と一瞬にして曲と競技にくいつきます。



それは曲への親近感であり、自分に近いものへの興味です。
そして、その音楽に対して感じる、“好きだな”“楽しいな”“ワクワクするな”というような気持ちが心に浮かび、ポジティブな気持ちで運動会の競技や子どもたちの姿を見てくれます。
それはまちがいなく運動会への満足感となります。
もちろん、すべての曲をみんなが知っているJ-POPなどにする必要はありません。



ただ、“ここぞというポイントで認知度の高い曲を使う”という技を知っておけばいいのです。
次は、運動会の曲の選び方についてです。
運動会のテーマから曲を選ぶ


運動会のBGMは、「テーマ✕音楽のジャンル」で考える。
これは、すでにみなさんが運動会のたびに自然とやられていることだと思います。



自分の園やクラスのテーマと音楽のジャンルをかけ合わせて曲を探していますよね。
たとえばこんな感じ。
海、忍者、祭り、世界の国、和、チャイナ、アラビアン、冒険、動物、魚、鳥、
のりもの、はたらくくるま、旅行、メルヘン、ファンタジー、空、飛ぶ、雲、風、
走る、泳ぐ、おばけ、妖怪、食べ物、やさい、くだもの、ピクニック、オリンピック、
カラフル、パーティー、おでかけ、ジャングル、大江戸、魔法、昆虫、海賊、宇宙、
絵本の世界、童話の世界、仲間、森の運動会、輪、きずな、友だち、スマイルなど
このようなテーマに合わせて、次は音楽のジャンルで探していきます。
具体的に言えば、
① J-POP
② J-POPのインストゥルメンタル(楽器の演奏のみ)
③ 洋楽
④ 子ども向け音楽(“おかあさんといっしょ”など)
⑤ ディズニー・ジブリ音楽
⑥ クラシック音楽
⑦ 映画のサントラ
⑧ ドラマのサントラ
⑨ アニメのサントラ
⑩ 効果音のCD
他にもあるかもしれませんが、思いつくかぎり書きました。



ジャンルにはそれぞれ特徴がありますので、それぞれのメリット・デメリットについて少しだけ説明します。
① J-POP
■メリット
・みんなが知っている曲が多く、大きな盛り上がりにつながる
・エンターテイメント性が高まる
■デメリット
・J-POPはTVや歌手などの色合いが強く、子どもの活動に適さない場合がある
・J-POPだけだと「先生の好きな曲ばっかり」と保護者に思われる可能性がある
・自分の趣味がバレてしまう(笑)
② J-POPのインストゥルメンタル(楽器の演奏のみ)
日本コロムビアから出ている“ヒットマーチシリーズ”のCDが代表的でしょうか。
■メリット
・歌詞がないので、子どもの姿だけに集中できる
・TVや歌手などの色合いを減らしつつ、保護者の興味を引きつけられる
■デメリット
・基本的なメロディーはほぼホーンの音なので、連続で使用すると印象が似てくることがある
③ 洋楽
■メリット
・歌詞の意味がわからない分、歌詞と楽器の音が合わさって1つのBGMになる
(インストゥルメンタルに近いものがある)
・有名な曲を選ぶと、“かっこいいイメージ”が共有されて盛り上がる
■デメリット
・誰も知らない曲だと「これは何の曲だろう?」と保護者が気になってしまう
④ 子ども向け音楽(“おかあさんといっしょ”など)
NHKの教育番組の曲や、最近は“ひろみち&たにぞう”の運動会CDもよく使われていますね。
■メリット
・子どもが知っている曲も多く、子どもの気持ちが盛り上がる
・誰もが安心して聞くことができる
・子どもらしい雰囲気の運動会ができ、保護者にとっても好ましい
■デメリット
・子ども向けの曲ばかりだとメリハリがつきにくいことがある
⑤ ディズニー・ジブリ音楽
■メリット
・J-POPと同様に多くの人が知っている
・ディズニーやジブリに対して感じる“キラキラ感”を競技に出すことができる
・子どもが知っている曲も多く、子どもの気持ちが盛り上がる
・エンターテイメント性が高まる
■デメリット
・ディズニー音楽はキャラクターなどの色合いが強く、子どもの活動に適さない場合がある
⑥ クラシック音楽
■メリット
・“かけっこの時はこれ”というような定番の曲がある
■デメリット
・全体的に静かな曲が多く、盛り上がりに欠けることがある
⑦ 映画のサントラ
■メリット
・大ヒットした映画のサントラなどは知っている人も多く、とても盛り上がる
・壮大でカッコいい曲がある
■デメリット
・1曲の中に、盛り上がる部分と静かな部分があって、使いづらいことがある
⑧ ドラマのサントラ
■メリット
・大ヒットしたドラマの曲は知っている人も多く、とても盛り上がる
・映画音楽に比べると1曲も長くなく、コンパクトにまとまっていて使いやすい
■デメリット
・音楽は良くても、ドラマの内容が子どもの運動会に適さない場合がある
⑨ アニメのサントラ
■メリット
・子どもが知っている曲も多く、子どもの気持ちが盛り上がる
・子どもらしい雰囲気の運動会ができ、保護者にとっても好ましい
■デメリット
・アニメ音楽はキャラクターなどの色合いが強く、子どもの活動に適さない場合がある
⑩ 効果音のCD
■メリット
・一般的な曲やサントラなどでは出せない音(効果音)を出せる
・効果音を使うことで細かい演出ができる
■デメリット
・効果音を1つ流す場合その前後で曲の切り替えになるので、無音になる時間が生まれる
まとめ


いかがでしたでしょうか。
みなさんが自然とやっている運動会の曲選びをまとめてみました。
このようなことを知らなくてももちろん曲探しはできますが、基準や基本的な考え方を知ることは意味があることだと思います。



みなさんの曲探しがすこしでもスムーズにいけば嬉しいです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。