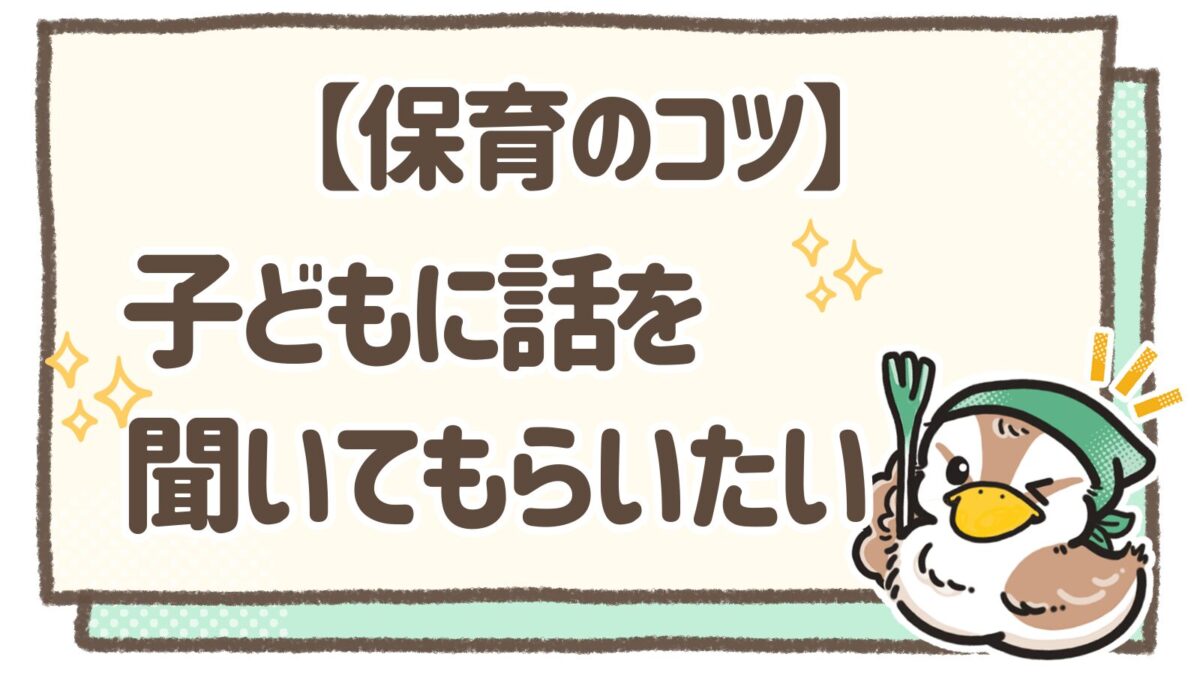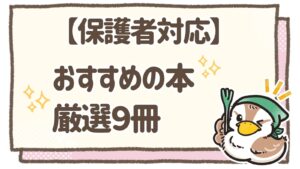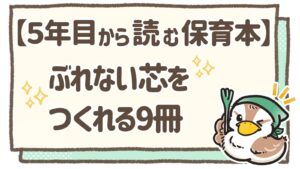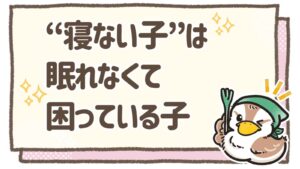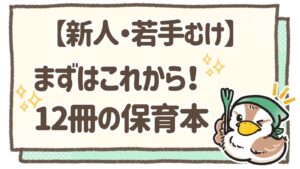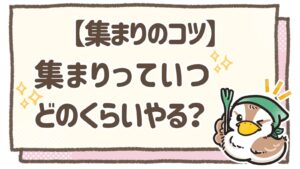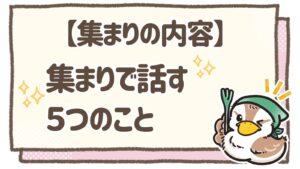さて、前編では日付や今日の活動、今後の予定など、“集まり”で話す基本的な内容を書きました。
この後編では、幼児クラス、特に4・5歳児クラス(年中・年長)で非常に重要な【話し合い・振り返り】についてまとめます。
 かもねぎ
かもねぎ就学に向けた力を養うとともに、今、保育に求められている“主体性”にもつながる大切なことになります。
それでは、始めます。
話し合い


① スタイル
② 進め方
③ 内容
④ 意味
“話し合い”とは、特に4・5歳児クラスに必要な経験です。
自分たちのことを自分たちで考える大切な活動です。
スタイル
・保育者と子ども
・子どもと子ども
4歳児クラスから5歳児クラスの始め頃までは、“保育者と子どもの話し合い”を繰り返していきます。
その積み重ねがあってこそ、子ども同士の話し合いにつながっていきます。



子どもだけで話し合えるのは、5歳児クラスになってからです。
ただ、5歳児クラスになればできるのではなく、4歳児クラスで“保育者ー子ども”の話し合いを積み重ねていればこそできることだと思います。



自分の意見を言う、友だちの意見を聞く、自分と友だちの意見のちがいに折り合いをつけていく、そのような力が育っていればこそできることではないでしょうか。
進め方
これだけが正解ではありませんが、例としてあげます。
① 担任からテーマを投げかける
② 子どもが意見を出す
担任はその意見をホワイトボードなどに書き出す(できれば絵も描けるといい)
③ 最後に担任が子どもの意見をまとめる
④ 結論が出る or 決まらなければ続きにする
「運動会の予行をやってみてどうだった?」などと、やってみたことの感想を出し合うこともあれば、子どもたちと何かを決める話し合いもあります。
前者ならば保育者が最後にまとめて終了ですが、後者だとなかなか意見がまとまらず決まらないこともあります。



そんな時のために、④の“決まらなければ続きにする”ということも、選択肢に入れておいてください。
なにも1回の話し合いですべてを決めなくていいのです。
「AもあればBという意見もあったね。じゃあ今日はここまでにしよう」と一度区切って、次に持ち越していいのです。
私の経験では、一定の時間がたてばすんなり決まったり、別のアイディアが出てきてそれに決まるということもありました。



4・5歳児クラスの話し合いに必要なのは、子どもたちの力を信じて待っことと、時間的余裕を確保することなのだと思います。
内容
大きくわけて3つあります。
(1) 子どもが考える・決める
例えば、その年の栽培物を何にするか決めたり、自分たちがどのような当番をしたいのか考えることです。
子どもたちが意見を出して、その後、保育者からの提案やジャンケン、多数決などで決めていきます。



“大人が決めたのではなく自分たちが決めたのだ”という思いは活動への意欲につながり、“自分たちは大きくなったぞ”という自信にもつながります。
(2) 身のまわりで起きたことを子どもたちに考えさせる
例えば、中身がごちゃごちゃに入っているままごと棚を見せて、「どう思うのか?」「どうやって片づけたらいいのか?」などとみんなで考えます。



つまり、子どもたちの身の回りで起きた問題や危険なことなどを伝え、それについてどう思うか、そして、どうしたらいいのかということをみんなで考え合うことです。
保育者は最後に意見をまとめて、“みんなでクラスの約束をつくった”という形につくります。
それは、“先生がつくった約束”より“自分たちでつくった約束”の方が子どもたちには意味があるからです。
もちろん完全に守れるわけではありませんが、「ねぇ、この前約束したよね?」と一言伝えるだけで、「あっ!」と思いだして気持ちを切り替えられる子が多いです。



このやり方のいいところは、子どもへの“注意”の言葉かけを減らせるところです。
「きれいに片づけて!」「またぐちゃぐちゃだよ」というのではなく、「みんなでつくった約束は何だっけ?」と投げかけることで、子どもたちに適切な行動を促すことができるのです。
これは大きいです。



私たち保育者はどうしても不適切な行動に注目しがちで、注意したり、時には怒ったりすることが多いのですが、子どもと一緒に“約束”を考ることでそれを減らすことができるのです。
(3)感じたことを伝えあう
例えば、運動会の予行の前日に「明日初めての予行だけど、今どんな気持ち?」と投げかけたり、予行後に「やってみてどうだった?」と子どもの思いや意見を出してもらうことです。



子どもたちからはドキドキする気持ちや楽しみな気持ちなどがあがり、クラス全体で思いを共有することができます。
詳しくは、この後の【振り返り】にありますのでご覧下さい。
意味
子どもたちは“話し合い”を通して、以下のようなことを学びます。
・自分の頭で考える
・自分の意見を言う
・人の意見を聞く
・みんなで決めること
・決めたことを守る
“話し合い”が子どもたちの習慣となっていると、ふだんのケンカなどでもお互いに意見を言ったり、まわりの友だちが「〇〇くんはどう思うの?」などと“話し合い”ができるようにもなります。
何かあれば友だちと話し合う。



そのような力を身につけて、小学生になってほしいですね。
振り返り
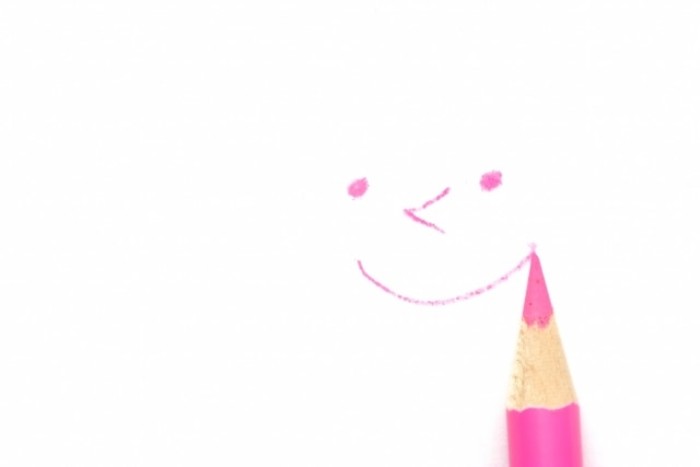
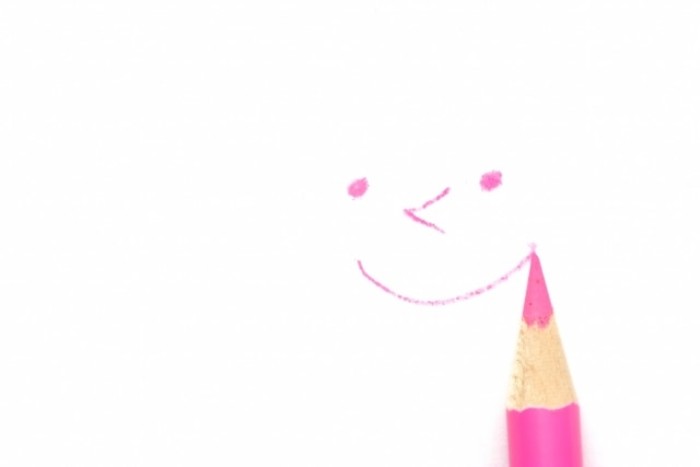
① 活動をみんなで振り返る
② 活動を【深める・定着させる・共有する】
③ 集まり → 活動 → 振り返り
“振り返り”とは、クラスみんなで活動した後に行われる“話し合い”です。



午前中に活動をして、自由あそび・昼食が済み、午睡前の集まりでやることが私はほとんです。
「今日〇〇(活動)をやってみてどうだった?」などと保育者が子どもたちに投げかけ、子どもたちの気持ちや考えをみんなで共有します。
そうすることで、活動への理解が深まり、次回への期待と工夫が生み出されていきます。
自分の気持ちを確かめる・友だちの気持ちを知る
具体的な例をあげてみましょう。



発表会に向けて、“3びきのこぶた”の劇あそびを行った後の場面です。
まずは、やってみた感想を聞きます。
担:「今日は、3びきのこぶたの劇あそびをやったよね。やってみてどう思ったかな?」
子:「楽しかった!」
子:「面白かった!」
子:「ちょっとドキドキした」
担:「そうだね。楽しい思いもあったし、ドキドキもしたよね」
楽しさもあれば緊張もあったという子どもの姿があげられました。
“楽しかった”という意見を聞いて、「私も楽しかったな」とその気持ちを強くする子もいるでしょう。
また、“ドキドキした”という意見を聞いて、
「あっ、ぼくもドキドキしたんだよな。よかったー、みんな同じなんだな」
「〇〇ちゃんもドキドキしたんだ。でもがんばってやってたぞ。私もがんばろう!」
などと、それぞれの胸の中で思いが広がることも予想されます。



振り返ることで、自分の気持ちだけでなく、友だちの思いにまで関心が広がり、活動への理解や意欲がさらに深まっていきます。
振り返りからさらなるあそびや活動につなげる
次にあげる例は、子どもたちが楽しんだことを、さらに具体的な形にするやり方です。
担:「3びきのこぶたあそびがおもしろかったという子がたくさんいたよね。」
「では、どんなところが面白かったのかな?」(質問)
子:「ふーふのふーで家を吹き飛ばすところ!」
担:「そうか。みんなはオオカミになって家を吹き飛ばすのが面白かったんだね」
「じゃあ、もう1回やってみようか?」
子:「やるー!!」
担:「じゃあ、先生がこぶたになるから、みんなは座ったままオオカミになってね」
「オオカミの“あーけーてー”からやってみようよ」(提案)
ここでは、保育者の質問により、“面白かった”ということをより具体的な形にしています。
そして、“劇あそびのやりとりで遊ぼう”と保育者が提案しています。



ここにはねらいが2つあります。
1つは、実際の劇あそびではその役をやれなかった子や、ドキドキして思うようにできなかった子も、このような“あそび”にすると、参加できることがあるからです。
もう1つには、再度やりとりを楽しむことで、劇の流れやセリフが子どもたちに定着しやすいからです。
時間と場所を変えて、再度“あそび”として繰り返すことには意味があると思います。



子どもたちが楽しんだ部分をみんなでもう1回遊んでみることは、あくまでも進め方の1つですよ。
最後にあげる例は、むずかしかったことを聞き、どうしたらいいかをみんなで考えて、次の活動につなげるやり方です。
担:「みんなは色々なことが面白かったみたいだね。」
「じゃあ逆に、うまくいかなかったところはあった?」
子:「セリフがバラバラになっちゃった」
担:「そうか。〇〇くんは友だちと一緒にセリフをいいたかったんだね」
「じゃあ、どうしたらみんなで一緒にセリフを言えるんだろうね?」
「みんな、どう思う?」
子:「せーの、でいえばいいよ!」
担:「そうか。“せーの”で友だちと合わせればいいんだね」
子どもたちに意見を出してもらい、楽しかったことはみんなで共有する。
むずかしかったことはみんなで考える。そして、次の活動につなげていく。
ここで保育者が行うのは、“質問すること”や“投げかけること”。



子どもに考えさせることが、私たち保育者の大切な役割だと思います。
それが、子ども主体の保育であり、環境づくりなのではないでしょうか。
ちなみに、振り返りにいたる理想の流れは、
①集まり:活動の見通しをもつ
②活動:“やりたい”という強い思いをもって活動する
③振り返り:感じたことを振り返りで言葉にして、みんなで共有する
という感じだと思います。
そして、
集まり → 活動 → 振り返り → 集まり → 活動 → 振り返り
というように、次から次へとリンクしてつながっていけば、子どもたちの中に経験値が積み重なり、大きな力になっていきます。
もちろん、“同じ活動をずっと続ける”という意味ではなく、“活動から得たことや感じたことを、別の活動にもつなげていく”ということです。



このようにして、“集まり”と“振り返り”というのはセットで行うのが望ましいと思います。
まとめ


主体性とは【子どもが考える・子どもが決める】
前編・後編を通して、保育の“集まり”で何を話しているかまとめました。
特に、活動や予定を知らせて【見通しを持たせる】ことや、話し合いや振り返りを通して【子どもに考えさえる・決めさせる】ことをねらう大切さを書きました。



それらがすべて“子どもの主体性”につながると考えるからです。
考える土台となる情報(見通し)を得られるようにし、子どもたちが自分たちで考え合って答えを出していく。
これが、これからを強く生きていく子どもたちに求められる力ではないでしょうか。
たくましい子どもたちを育てる環境づくりができるように、これらの記事が参考になれば嬉しいです。



最後まで読んでくださり、ありがとうございます。