 かもねぎ
かもねぎこんなお悩みを解決します。
この記事では絵本の内容だけでなく、対象年齢や文字の分量についてもまとめているので、忍者の絵本を探している保育園や幼稚園の先生にぴったりです。
16年の保育士経験の中で、何十人の子どもたちに読み聞かせをしてきた忍者の絵本を紹介しています。
- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 小さい頃から図書館が大好き


- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 小さい頃から図書館が大好き


記事の前半では忍者ごっこや運動会、発表会につながるような絵本を、後半では笑いや感動だけでなく「食べ物✕忍者」の絵本まで紹介しています。
「みんなで忍者になって身体を動かした」「運動会や発表会で”忍者”をテーマに盛り上げたい」と思っている保育士さんや幼稚園の先生はぜひご覧ください。
✅ 絵本の紹介ポイント
- 【年齢】読み聞かせやすい年齢
- 【文字量】文字の多さ
(少ないーふつうー多い) - 【特徴】絵本の特徴まとめ



絵本のタイトルの横には、その絵本のテーマも抜き出しています。
「任務」「運動会」「変身」「お弁当」などのテーマからも絵本を探せますので、あわせてチェックしてください。
忍者あそびのすべてがこの1冊に入っています
忍者あそびがいっぱい
【年齢】2歳児クラスから小学校低学年まで
【注意】この本は絵本ではありません
【特徴】子どもたちと忍者ごっこをするための仕掛けがつまっている保育者のネタ帳
「子どもたちと忍者ごっこをしたいけど、何から始めたらいいでしょうか?」という方はもちろんのこと、
「大きな声じゃ言えないのですが、子どもたちとどうやって遊んだらいいか正直わかりません」という方にもおすすめの1冊。
なぜなら、この本にのっているあそびや制作をやれば、子どもと楽しく忍者ごっこがまちがいなくできるからです。



これは保育士歴16年の主任保育士だった私が、自信をもって言えることです。
この本の内容を書きだすと以下の通りです。
・忍者道具の制作やおもちゃ作り18種
・忍者というイメージを組み込んだ集団あそび、運動あそび、プールあそび
・忍者劇の小道具や背景づくり
・忍者のあそびうた(楽譜つき)
・忍者スタンプラリー
・忍者のパネルシアター、紙皿シアター、スケッチブックシアターのつくり方(型紙つき)
・忍者の変身カードづくり(型紙つき)
忍者あそびのすべてがこの1冊に入っているといっても過言ではない内容になっています。
✅おすすめの使い方
この本は保育者のネタ帳です。
ネタ帳を使って忍者あそびの準備をしつつ、子どもたちの期待を高める絵本を読み聞かせるのがおすすめです。
以下、具体例です。
① 忍者絵本の読み聞かせで、「忍者になりたい」という子どもたちの思いを引き出す
② 『忍者あそびがいっぱい』で紹介されている忍者道具の制作、集団あそび、各種シアターなどを楽しむ
③ 子どもの中で“忍者”へのあこがれが強くなり、「もっとやりたい!」という思いが生まれる
④ さらに『忍者あそびがいっぱい』のネタで遊んでいく
2歳児クラスから年長はもちろんのこと、小学校低学年くらいまで十分に遊べます。



「子どもたちと忍者ごっこをやりたい」と思っている保育士や幼稚園の先生におすすめの1冊です!
✅【スケッチブック・シアター】にんじゃしゅぎょうだ、いち、にの、さん!
忍者ごっこであそぶ絵本の第2弾が出ていました。
こちらは忍者の修行にスポットをあてており、水遁や木遁の術、手裏剣でやっつけるなど、子どもたちのあこがれる忍術がたくさんでてきます。



子どもたちは絵本のストーリーの中で保育者の呼びかけに応えながら、かっこいい忍術をつかって、声をあわせたり体を動かしたりして遊べる1冊となっています。
著者の浦中こういちさん実演の動画がアップされていたので、具体的な遊び方などの参考にどうぞ。
ワンフレーズの歌とポップなイラスト、楽しい修行などに子どもたちが大喜びするのが目に浮かびます!
また、保育者視点で言うと、



保育園や幼稚園の発表会・劇で忍者系をやるならば、この歌や忍術はまちがいなくつかえます!
子どもたちの劇では言葉だけで進行するのはむずかしいもの。
セリフの合間にこのようなワンフレーズの歌やあそびを組み込んでいくことで、物語はリズミカルに進みます。



忍者の劇を考えている保育園・幼稚園の先生方に、この本はおすすめです。
どきどきわくわく冒険絵本
にんじゃつばめ丸を中心に、3冊紹介します。
にんじゃつばめ丸(忍者×修行×運動会×勇気)
【年齢】4歳・5歳児クラス
【文字量】ふつう
【特徴】ストーリーもわかりやすく、すぐにごっこあそびができる(忍者の修行・忍者運動会・ストーリーの再現)
どこにでもある普通の家に住んでいるお父さん、お母さん、そして3人の子どもたち。
しかし、ひとたび家に戻ると、バサッと忍者装束に身をかため、忍者一家に大変身します。



そして、すぐに忍者の修行が始まります。
廊下をきつね走りの術で子どもたちが駆け抜けると、秘密の床下からおもむろに刀を取り出す父上。
庭では手裏剣を投げ、へいの上から布を広げてむささびの術のように空中ジャンプ!
「もしかしたら、本当にこんな一家がどこかにいるのでは?」と思わずワクワクドキドキしてしまう展開になっています。
物語の後半では、全国の忍者が富士山に集まって“忍者の大運動会”をするという熱い展開がスタート。
つばめ丸とライバル・がまのしんとの白熱するデッドヒートがこの絵本の山場になります。
私が年長クラスで読み聞かせをした時は、熱い勝負とラストのシーンでつばめ丸がふりしぼる勇気に、子どもたちも思わず息をのんで絵本を見つめていました。
『にんじゃつばめ丸』は第2巻もあるのですが、どちらの本も4・5歳の保育におススメです!
理由は2つ。
① “忍者のごっこあそび”ができる
・子どもたちは忍者が大好きなので、きっかけがあれば忍者にすぐなれる
・私の年長クラスでは、読み聞かせをしたら庭で“つばめ丸ごっこ”が始まりました
・担任も誘われたので、ごっこあそびに参加しつつ、ストーリー進行を補助しました
②“忍者の修行”というイメージを【子ども・担任】で共有できる
・どんな活動も“忍者の修行”と呼ぶと、わくわくする楽しいあそびになる
・私の年長クラスでは、運動会に向けた運動あそびを“忍者の修行”にしています
・「よしっ、今日は忍者の修行をするぞ!みんなできるかな?」などと呼びかけると、「かんたんだぜー!」「絶対できる!」などと子どもたちもやる気を高めています



読んだ時もその後も、子どもたちと一緒に目いっぱい楽しめる絵本です。
にんじゃつばめ丸 はつにんむの巻(忍者×任務×たたかい×日本の名所)
【年齢】4歳・5歳児クラス
【文字量】ふつう
【特徴】ごっこあそびができる(忍者の任務ごっこ・忍者のたたかいごっこ)
上記のポイントや保育でつかえるポイントも『にんじゃつばめ丸』と同様です。
「これをじじ上に届けるのだ」と父上から渡された秘密の巻物。
ライバルのがまのしんたちに巻物を奪われないように、無事に琵琶湖のじじ上のところまでたどり着くことができるのか・・といった、わかりやすくも、わくわくどきどきする楽しいストーリーとなっています。



また、つばめ丸だけでなく、その兄弟のからす丸やこかも丸も大活躍!
場面も東京から西へ西へと移っていき、横浜や名古屋、関ヶ原合戦場などと日本の名所をつばめ丸たちと巡っていき、最後は琵琶湖の中に飛び込んで…、大迫力と笑いのラストです。
つばめ丸シリーズ第2巻の大きな特徴は以下の2つ。
・忍者の道具をたくさん使った戦い
・任務が成功すると“みならい忍者”になれる
戦いもさることながら、「〜をクリアするとみならい忍者になれる」というシチュエーションは子どもたちの大好物!
「ふっふっふ…、これができたらみならい忍者になれるぞよ」などと一声かければ、運動あそびでも生活の中のことでも、子どもたちは張り切って取り組んじゃいます。
絵本を読んで子どもたちと忍者ごっこのイメージを共有し、色々なことを楽しくできるといいですね。



ぜひ、1・2巻合わせて読まれることをおすすめします。
わんぱくだんの にんじゃごっこ(忍者×忍者道具×ファンタジー×忍者に変身・忍者ごっこ)
【年齢】4歳・5歳児クラス
【文字量】ふつう
【特徴】忍者に変身できる(布・新聞紙・折り紙)・ごっこあそびができる
知っている人は知っている“わんぱくだんシリーズ”。私は最近知りました。
“けん・ひろし・くみ”の3人の子どもが集まると、いつも何かがおこりだす。そんなファンタジーがつまったシリーズです。
この絵本ではふろしきにダンボール、新聞紙、折り紙などで忍者に変身してごっこあそびをする3人が、ふとしたことからお城がある世界に忍者になって迷い込む展開になっています。
子どもたちにとっては、まるで自分たちが不思議な世界に入ってしまったようなわくわく感が感じられるストーリーです。
そして、それ以上に子どもの興味をひくのは、わんぱくだんの3人が身近なものを使って忍者に変身する場面だと思います。
布を頭に巻いて覆面にし、新聞紙で刀をつくり、折り紙で手裏剣をつくる。
保育園や幼稚園によってはこのようなあそびがNGなところもあるでしょうが、もしOKならば、この絵本を読んでから“忍者になってみよう”と制作を始めても楽しいと思います。



子どものあそび心、変身願望をがっつりつかむ絵本です。
わっはっは!おもしろ絵本
どじにんじゃ(忍者×笑い×忍術×動物)
【年齢】3歳・4歳・5歳児クラス
【文字量】少ない
【特徴】くり返しのパターンで大笑い・子どもがもう1回読みたくなる
くろひょう忍者のかげまるが、ふくろう忍者とともにお姫様を助けにいくわかりやすいあらすじです。
かげまるは子どもたちも知っているおなじみの忍術を使って敵の城まで忍び込むのですが、タイトル通りのどじさで失敗に次ぐ失敗。



1つひとつの忍術がいろいろな理由で失敗していくところがこの絵本の面白いところです。
中盤以降、そのくり返しの流れが子どもたちもわかってきます。
すると、「また、失敗するぞ・・今度はどんな失敗かな?」と先の展開を期待しながらわくわくして待つようになります。
この絵本の楽しさを知ったわが家の年長の息子も、寝る前の絵本タイムに何度も『どじにんじゃ』を選んでいました。



子どもたちが“もう1回あの面白いのを見たい”と思ってしまう、爆笑必死の絵本です。
いかにんじゃ(忍者×海の生き物×海賊×言葉あそび×笑い)
【年齢】3歳・4歳・5歳児クラス
【文字量】ふつう
【特徴】言葉あそびにつながる・忍者×海×海賊という間口の広さ
ストーリーはいたってシンプル。
海辺の村に“いかにんじゃ”がやってきて、村をおそってきた海賊(貝賊)を刀や忍術でやっつける話です。
しか~し、忍者や海賊がみんな海の生き物で、話のいたるところに海の生き物の言葉あそび(ダジャレ)が入り、最後まで笑いの絶えない内容となっています。
例えば、「あさりは、あっさりやられ・・」「かきは、かきーんと割られ・・」などという具合です。(←文章だけだとアレですが、絵本では面白いのです!)



そして、内容がシンプルならば、絵もはっきりしていてポップ。見やすいです。
全てがわかりやすく面白くできている絵本で、3歳児から5歳児クラスまで楽しめます。
この絵本のすごいのは、子どもの好きなものをつめこんだところです。
忍者に海賊、海の生き物、海、言葉あそび(ダジャレ)、食べ物・・。
あまりに言葉あそびが面白いので、読み聞かせ後に子どもたちが自然とまねっこをして、言葉あそびを始める可能性が高いです。(現に私のクラスではそうでした)



お話の面白さだけでなく言葉あそびにも興味を持ってもらえるので、4・5歳時クラスには特におすすめです。
にんじゃサンタ(忍者×サンタ×修行×クリスマス×空想×笑い)
【年齢】3歳・4歳・5歳児クラス
【文字量】少ない
【特徴】にんじゃサンタごっこができる(他にはないごっこあそび!)
この絵本の表紙を見た時、どんなストーリーなのかまったく予想がつきませんでした。
読んでみると、“にんじゃサンタ”という奇妙な人たちが、走って跳んで手裏剣を投げて修行に励んでいます。
「それで、どうなるのかなぁ?」と不思議な感じでしたが、中盤で話がクリスマスイブになるとその修行の意味がやっとわかります。
・走ったり跳んだりする修行は、プレゼント配りで町中を疾走するため。
・手裏剣を投げる修行は、プレゼントを子どもたちの枕元にピタリと投げて届けるため。
つまり、サンタクロースとしてみんなにプレゼントを届けるために、一生懸命修行していたのです。
最初の「?」が大きいだけに、理由がわかると「なるほど~」「確かに!」と納得してしまいます。
そんな面白い内容が、個性的で動きのある絵やダイナミックな色使い、短くもリズムのある言葉でつづられているのがこの絵本です。
1度見たら忘れられない絵やタイトルが、子どもたちの心にも響きます。



クリスマスシーズンにこの絵本を読んで、担任も加わっての“にんじゃサンタごっこ”は大盛り上がりまちがいなしです!
【1・2歳むけ】ぱぴぷぺぽーず(忍者×体を動かす×まねっこ×語感を楽しむ)
【年齢】1歳・2歳クラス
【文字量】少ない
【特徴】小さいクラスの子でも、「忍者のイメージ×まねっこ遊び」を楽しめる
こちらの絵本は乳児向けで、『だるまさんが』に似ている”語感やまねっこを楽しむ本”です。
「だ・る・ま・さ・ん・が…、びろーん」という、これです。
✅『だるまさんが』
『ぱぴぷぺぽーず』では、「ぱぴぷぺぽーずの……、ぱっ!」というフレーズと一緒に、かわいい忍者たちがポーズをとります。



体を動かしたり、友だちと触れ合ったり、思わず笑っちゃうようなポーズをとったりと、1・2歳の子どもたちの心をぐっとつかむ絵本です。
日々の読み聞かせの中で読むのも楽しいですが、
・2歳児クラスで【忍者】のイメージで遊びたい
・幼児クラスが忍者のイメージで劇あそびや運動をやっている時に、1~2歳クラスでも【忍者】というテーマで遊びたい
そんな時にも子どもたちと楽しめる内容になっています。



乳児クラスでも【忍者】というイメージで遊び出すきっかけをつくれる楽しい絵本です!
心にじんわりしみる絵本
ニンジャさるとびすすけ(忍者×殿さま×勉強とあそび×いじめ×生と死)
【年齢】5歳児クラス
【文字量】多い
【特徴】子どもが抱える悩みに1つの答えをくれる(特に就学後の)
どこかで見たことがある絵だと思ったら、『おまえうまそうだな』『おとうさんはウルトラマン』などを描いている宮西達也さんの絵本でした。



この絵本では、あの有名な“さるとびさすけ”の孫、“さるとびすすけ”が主人公。
“すすけ”はニンジャ団のお頭である父のもと、大勢の子分ニンジャたちと暮らしています。
“すすけ”は色々なことに悩むので子分たちも一緒に考えますが答えが出ず、自分たちが守っているお城のお殿さまに聞きに行く、というストーリーになっています。
この“すすけ”の悩みですが、“勉強とあそびはどちらが大切か”、“いじめをなくすにはどうしたらいいか”、“死んだあとはどうなるのか”というなんとも大きなものなのです。
そして、お殿さまが“すすけ”の悩みに答えを出してくれるのですが、これがまた深い!
“にんじゃ”というモチーフやかわいくて見やすい絵が、むずかしいテーマを子どもの心に届きやすくしています。



子どもだけでなく、大人の心にもじんわりしみる素敵な絵本です。
あかにんじゃ(忍者×変身×予想外の展開)
【年齢】5歳児クラス
【文字量】ふつう
【特徴】想像力や絵本の楽しさが広がる
絵本といってもいろいろなタイプがありますが、この『あかにんじゃ』は非常に独特。
赤い装束の忍者やお城、お侍さんなどが出てくる冒頭はとても“にんじゃ”らしく、シンプルで繰り返しのある展開はとてもわかりやすいです。
それが気づくと、スポーツカーやおまわりさんまで出てきてしまうまさかの展開!
シュール系の絵本といえば収まりがいいですが、なんともへんてこりんな世界が広がっています。
子どもたちからするとあれよあれよと言う間に場面が展開し、想像する物語を面白い方に裏切られ、夢中になって絵本を見つめることになります。



「こんな絵本があるんだ!!」という発見や絵本の面白さ、奥深さを子どもに感じてもらえる1冊です。
想像広がる!空想絵本
てのりにんじゃ(忍者×修行×友情×夢がある)
【年齢】4歳・5歳児クラス
【文字量】多い
【特徴】夢やイメージが広がり、わくわくする絵本
「“てのりにんじゃ”ってなんだろう?」「手のひらサイズの忍者がいたら面白いな」という思いやイメージが広がる絵本です。
“もし、てのりにんじゃにであったらどうしたらいいのかしっておきましょう”というところから物語は始まります。
そして、てのりにんじゃと仲良くなる方法や忍者だんごの作り方、修行を手伝う方法など具体的に詳しく説明してくれます。
“てのりにんじゃ”の世界を広げつつ、話の終盤は、男の子とてのりにんじゃとの友情の物語にもなっていきます。



イメージを広げる楽しさだけでなく、思わず自分も“てのりにんじゃ”に出会いたくなる、素敵な絵本になっています。
思わず食べたい!たべもの絵本
にんじゃべんとう(忍者×おにぎり×お弁当×忍術×ピクニック)
【年齢】3歳・4歳・5歳児クラス
【文字量】少ない
【特徴】遠足やピクニック、お弁当づくりに楽しくつなげられる
にんじゃむらの“にんじゃおむすび3きょうだい”がゆかいな忍術を使って、色々なたべものくんたちを美味しいお弁当にしてしまうお話です。
絵もほんわかしていてかわいいし、ストーリーもシンプルなので、2歳児クラスからでも楽しめるような内容になっています。



お弁当づくりごっこや遠足ごっこ、本当の遠足の前など、保育の中でも色々なシチュエーションで読みたい絵本です。
ぜひ、1度読んでみてください。
おりがみにんじゃ(忍者×おりがみ×和菓子×あんこ×殿さま×姫×和風)
【年齢】3歳・4歳・5歳児クラス
【文字量】多い
【特徴】おりがみあそびや、あんこを中心とした和菓子への興味を広げられる
物語は、おりがみにんじゃがあずきの国の城に忍び込み、幸せになれる宝物をみつける話です。
私はタイトルから“おりがみ”と“にんじゃ”がメインだと思って読んでいたのですが、意外にも、美味しそうな和菓子(それもあんこ系の)がふんだんに描かれていました。
特に、和菓子でつくられたようなお城が子どもの興味をぐっと引きます!
まるで、ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家のようです。う~ん、食べたい!
絵本の中には作中にでてくるおりがみの折り方ものっています。



読み聞かせ後におりがみをやってもいいですし、美味しそうなお城を描いたり和菓子の話で盛り上がるのも楽しそうです。
また、おりがみ殿さまのお城はすべておりがみでできており、カラフルできれい。
おりがみが得意な子が「わたしもおりがみでお城がつくりたい!」と言い出すかもしれません。
そのくらい、魅力がある絵本だと思います。
まとめ
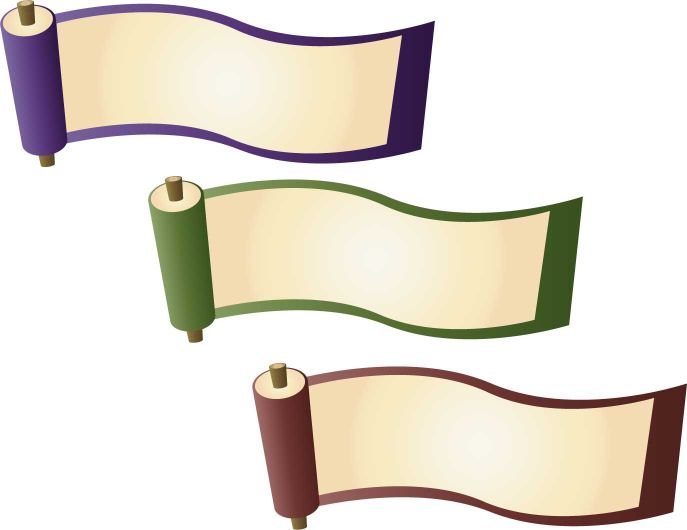
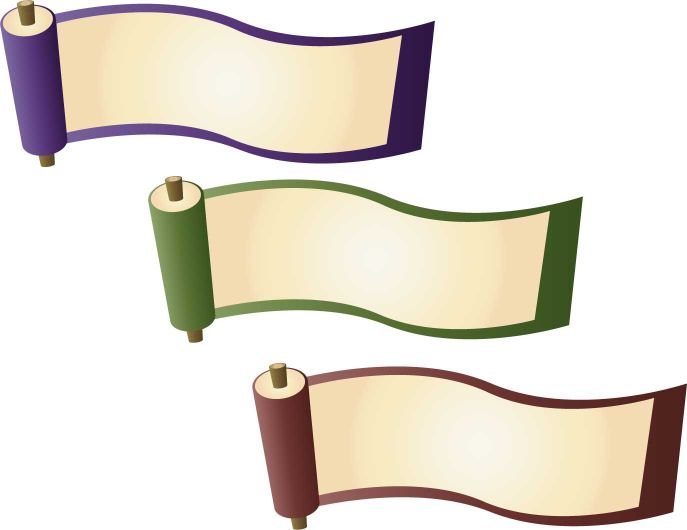
子どもたちの大好きな忍者の絵本。
ここに紹介したのはほんの一部。今後も増やしていきたいと思います。
また、保育に役立つようにと読み聞かせ後のあそびも書いてありますが、それも例えばの話です。
保育者側がねらいを持って読み聞かせる場合もあれば、絵本を楽しんだ子どもたちが自然発生的に物語のごっこあそびを始めることもあります。



まずは、絵本そのものを保育者も子どもも楽しむことが大切ですよね。
これからも、様々なジャンルの絵本を保育者の視点から紹介していきます。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。






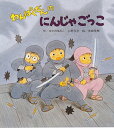





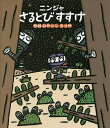



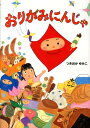


コメント