この記事を読むと保育園や幼稚園での「集まりの基本的なやり方・考え方」がわかります。
 かもねぎ
かもねぎ子どもの主体性を育むために「集まり」をベースとした取り組みを実践してきた経験をもとに記事を書きました。
- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 主体性を大切にする保育を実践


- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳まですべて経験
- 主体性を大切にする保育を実践


記事の前半では「いつ・どうやって」という集まりの疑問を解説し、後半では「3歳〜5歳児クラスでの集まりの違い」や「集まりがうまくいかない理由」などをまとめています。
「集まりで子どもたちに集中してほしい」「集まりに苦手意識がある…」と思っている保育士さんや幼稚園の先生はぜひご覧ください。
集まりはいつ、どのくらいの時間やるのか?


① 活動の前や生活の区切りに行う
② 集まりの時間は5分~20分ほど
詳しく解説していきます。
いつ集まりをやるのか
園によって異なる場合もありますが、たいてい「午前・お昼・午後」に集まりをする機会があります。
具体例をあげると以下の通りです。
【午前】 室内あそび→片づけ→排泄→集まり→戸外あそび
【お昼】 昼食→排泄→集まり→午睡
【午後】 戸外あそび(室内あそび)→着替え→排泄→集まり→当番保育(遅番)
その日の活動やねらいによって、どの時間にどのくらいの集まりをするかを考えます。



わたしは“興奮する子どもたちの気持ちを切り替える”ことや、“見通しを持って主体的に生活する”ために、ほとんどの場面で集まりをしています。
時には、遊ぶ時間の確保のために朝の集まりをしないで遊び続けることもありますが、その場合も、事前に以下のようなことを子どもたちに伝えています。
“今、何をするのか”
“いつ、次の行動に移るのか”
“その後、どうなるのか”
子どもたちが自分で考え、判断できる情報をわかりやすく伝えることを大切にしています。
どのくらいの時間集まりをやるのか
決まった答えはありませんが、その日や週の活動、子どもの年齢やその日の状態などによって、臨機応変に行います。



ただ、子どもの集中時間は限られているので、5分~20分ほどでしょうか。
子どもたちが楽しく、集中して参加できる範囲が望ましいですね。
集まりは3・4・5歳児クラスでどう変えるのか?


① “子どもの発達・クラスの様子”に合わせて変える
② 集まりの“時間・内容・子どもの役割”を変える
3歳児クラスだからこれ、4歳児クラスだからこれ、というようにカッチリとした答えがあるわけではありません。



あえて言うならば、みなさんの目の前の子どもたちが受け取れる内容が正解だと思います。
集まりの“時間・内容・子どもの役割”を変える
それを大前提としたうえで、“子どもの発達やクラスの様子に応じて、集まりの時間・内容・子どもの役割を変える”ということをかんたんにまとめます。
① 時間を変える(短い → 長い)
・クラスの子どもたちの集中時間に応じて、5分~20分くらいの集まりにする
② 内容を変える(あそび → 活動)
・クラスみんなが楽しめる“あそび”から始める
・“あそび”を通して【聞く・見る・話す・考える】を経験できるようにする
・徐々に“お知らせ”や“話し合い”などを通して【聞く・見る・話す・考える】を経験できるようにする
③ 子どもの役割を変える(観客 → 部分参加 → 子ども主体)
・最初は“あそび”を中心にして、【見る・聞く・話す・考える】を楽しめるようにする(観客・部分参加)
・“お知らせ”や“話し合い”などを行い、部分的に【見る・聞く・話す・考える】ことで参加できるようにする(部分参加)
・“お知らせ”や“話し合い”などを通して子どもが【見る・聞く・話す・考える】を行い、自分たちで活動をつくりだせるようにサポートする(子ども主体)



大きな流れをまとめました。
まずはあそびから始めて、基本の力をつけられるようにする。そして、保育者がリードして徐々に子どもが参加できるようにして、そのサポートを少しずつ減らしていく。
ここがポイントであり、むずかしいところでもあります。



大事なことは毎日の積み重ねであり、少しずつ“集まり”を広げていくことだと思います。
子どもの集中が続かない3つの理由と対策


“集まり”のポイントは、子どもをいかに集中させられるか。
幼児クラスの集まりは10人、20人以上の子どもを一斉に集中させて、しかも、その集中を5分、10分続かせることが求められます。



そう簡単なことではないですよね。
では、どうしたらいいのでしょうか?



子どもの集中が続かない3つの理由とその対策から考えていきましょう。
理由① 保育者の話が長い
自分でも気づかずにやっているのが「話が長い」です。



わたしも若いころは先輩に指摘されていました…。
5年、10年と繰り返すことでわかってきた対策は以下の通りです。
文章を短く切る
・「〜して、〜して、それで〜して」などと文章を長くしない
・話を短く区切り、1つの文章で伝えることは1つにする
・必要なことだけを話し、不必要な言葉は削る
予告する
・話の最初に「大事なことを2つ話すよ」などと予告して、子どもが聞きやすい環境をつくる
事前準備をする
・事前に話のポイントをまとめておく
・箇条書きのメモをつくって見ながらやる



とくに「事前準備」が大切ですね!
理由② 保育者の話にあきてしまう
4歳児や5歳児といってもまだ幼いので、話を聞き続けるとどうしてもあきてしまい、どんどん集中力が落ちていきます。



具体的な対策は次の3つです!
話し方や言葉選びを工夫する
・“小声を使う”“緩急をつける”“間を開ける”などと話に変化をつけて、子どもの集中をひく
・子どもにとってわかりやすい「簡単な言葉」で話す
子どもを「聞くだけ」にさせない
・保育者がずっと話していると、子どもは“聞くだけ”になってあきる
・子どもが“見る”“話す”“体を動かす”“考える”などもできるような内容にする
情報を目で見えるようにする
・絵や音、人形、身振り手振り、表情など、「言葉以外のもの」もつかって伝える



ペープサートを使用したり、ホワイトボードにイラストを描いて伝えるなど、子どもが「目と耳」を使って話を聞く環境を作ると効果が高いです。
理由③ そもそも始めから集中していない
集まりの始めから落ち着かない場合は、その前の段階に問題があります。



対策としては3つあります。
たっぷり遊ぶ
・十分に遊んだ子どもたちは満足感を感じて、その後の集まりにも集中しやすくなる
身体をたくさん動かす
・汗がにじむくらい身体をたくさん動かしてから集まりを行う
・運動をするとスッキリして、その後の集中力が高まる
遊びから集まりを始める
・どうしても落ち着かないときは、手あそびやパネルシアターなど子どもにとって楽しいあそびから始めて、集中しやすい環境をつくる
集まりを楽しくして「子どもの主体性」を育てよう


① 子どもの年齢や発達、その日の状況によって内容や時間を合わせる
② 「遊び→部分参加→子ども主体」の流れで集まりを発展させる
③ 子どもの集中が続かない場合は理由があるので対策を行う
保育者がただ話すだけでは集まりは難しいので、事前準備が大切になります。



そんな時間、取れないなぁ…。
事前準備といっても、
・明日は散歩に行こう
・散歩の注意点を3つ伝えよう(手をつなぐ・走らない・抜かさない)
・「3つの約束があります」と集まりの最初に予告しよう
はじめはこれくらいでOKです。



少しずつで良いので事前準備をやって、だんだんと習慣化することが大切です。
まずは小さな行動から始めるだけで大きな成長につながっていきます。



まずはやってみてくださいね。




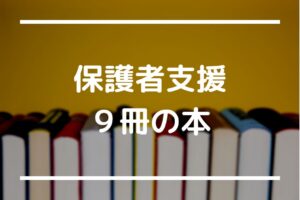
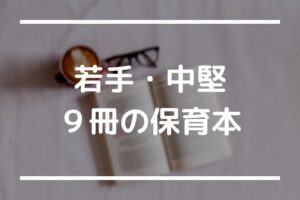
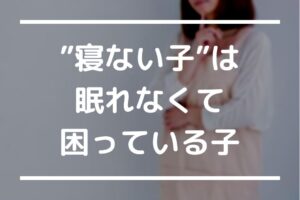
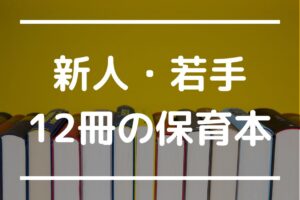


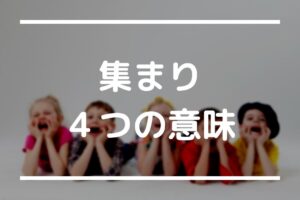
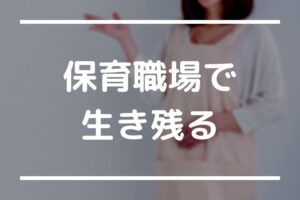
コメント