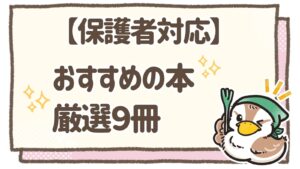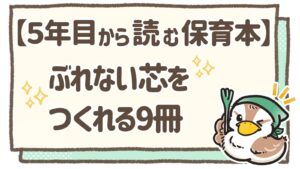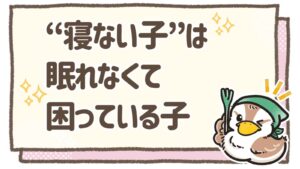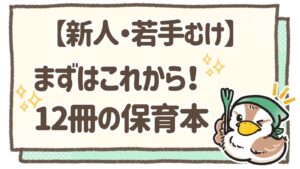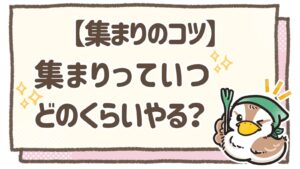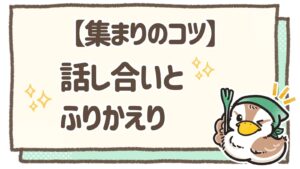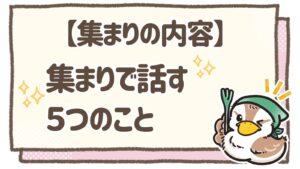保育士さん
保育士さん保育がうまくいかないことが多くて悩みます…。先輩みたいに子どもをひきつけるにはどうしたらいいの?
こんなお悩みに答えます。
✅ この記事で解決できるお悩み
- 子どもを活動に集中させるのが難しい
- 伝えたいことが子どもにうまく伝わらない
- 予想外のことが起きるとパニックになってしまう
- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳、フリーまですべて担任
- 公立、小規模園など様々な現場を経験


- 保育歴16年の保育士
- 0歳から5歳、フリーまですべて担任
- 公立、小規模園など様々な現場を経験


こんにちは!16年間、保育現場で子どもたちと走り回ってきた、保育士のかもねぎです。
実は私も若いころは失敗の連続で、「どうして保育がうまくいかないんだろう…」とよく悩んでいました。
でも、たくさんの失敗と工夫を重ねる中で、わかったことがあります。
- 子どもとの信頼関係がすべての土台
- 子どもへ話すときは「短く・具体的に」
- トラブルは「うまくいかない場合の想定」と「子どもの観察」で乗り越える
かつての私と同じように悩んでいる若手の先生に向けて、これまでの試行錯誤をまとめます。



明日からすぐに試せる具体的な解決策を、私の経験を交えながらたっぷりお伝えしますね。
保育がうまくいかない3つの理由


まず、安心してください。「うまくいかない」と感じるのは、あなたが保育士に向いていないからではありません。



それは、多くの若手保育士が必ず通る道なんです。
では、なぜうまくいかないと感じてしまうのでしょうか。
よくある3つの原因を見ていきましょう。
子どもを集中させられない
いざ絵本を読もう、活動を始めようと思っても、子どもたちがザワザワ…。
なかなかこちらを向いてくれない。



これは本当に「あるある」ですよね。
子どもたちの興味や関心は、常に移り変わっていきます。
その興味のアンテナを、グッとこちらに向けるための「ひと工夫」が、まだ少し足りないだけかもしれません。
伝えたいことが伝わらない
「片付けをしてね」「順番に並んでね」と伝えても、子どもたちの反応はイマイチ。
大人の言葉で、一度にたくさんのことを伝えてしまっているのが原因かもしれません。



子どもたちが理解できる言葉の物差しは、私たちが思っているよりも、ずっとシンプルだったりします。
伝えたい気持ちが強いほど、つい言葉が多くなってしまうんですよね。
予想外の出来事に焦ってしまう
子どもたちの行動は、まさに予測不能!
おもちゃの取り合いでケンカが始まったり、突然泣き出したり…。



そんな時、頭が真っ白になって、どう対応していいか分からなくなってしまう。
経験が少ないうちは、想定外の出来事への対応パターンが少ないため、焦ってしまうのは当然のことなんです。



では、いよいよ具体的な対策をお伝えします。
保育のコツ①:集中力を引き出す


子どもたちの心をグッとつかみ、集中力を引き出す3つの具体的な方法をご紹介します。
手遊びやゲームで注目を集める
何かを始める前に、まずは子どもたちの視線を集めることが大切です。
そんな時に大活躍するのが、手遊びやちょっとしたゲーム。
「はじまるよ、はじまるよ♪」と歌い始めたり、「先生のまねっこゲーム!」と体を動かしたり。
ほんの1〜2分でいいんです。
このワンクッションがあるだけで、子どもたちの意識は「これから何が始まるんだろう?」と、あなたに集中します。



レパートリーは少しずつ増やしていけば大丈夫ですよ。
「大好き!」と思われる先生になる
子どもたちは、やっぱり大好きな先生の話を聞きたいもの。
では、どうすれば「大好きな先生」になれるのでしょうか?
答えはとてもシンプルです。
- 子どもと一緒に、保育士も楽しんで遊ぶ
- 子どもの目を見て、笑顔で話す
- 一人ひとりの名前をたくさん呼ぶ
特別なことではありません。
日々の保育の中で、子ども一人ひとりと丁寧に関わり、「あなたのことを見ているよ」「あなたのことが大切だよ」というメッセージを態度で伝え続けること。



この積み重ねが信頼となり、「大好きな先生が話してるから聞こう!」という気持ちにつながります。
子どもの気持ちを聴いて信頼関係を築く
子どもが何かを話している時、やることが多くて、つい話を先に進めようとしていませんか?
ここで大切なのは、子どもの「話を聞く」だけでなく、その裏にある「気持ちに耳を傾けること」ことです。
- ブロックが崩れちゃったんだね。悔しかったね。
- お花見つけたんだ!きれいだね、嬉しいね。
- 怒ってたのは、友だちと一緒に遊びたかったからなんだね。
言葉にならない気持ちを代弁し、共感することで、子どもは「先生は僕の気持ちを分かってくれる」と感じます。



聴いてもらえる嬉しさは「話を聞こうとする姿勢」につながります!
次は、「集まりなどでどう話すか?」をお伝えします。
保育のコツ②:子どもに伝わる話し方を身につける


一生懸命な気持ちが空回りしないために、「伝わらない」を「伝わる!」に変える、話し方のコツを3つお伝えします。
子どもがわかりやすい言葉を使う
例えば、お片付けのとき。
「元の場所に戻して」と言うよりも、「ブロックさんのおうちに帰してあげようね」という方が、子どもたちはイメージしやすいですよね。
他にも、つい大人の言葉で指示してしまう場面はありませんか?
- 「ちゃんと並んで!」 ではなく 「みんなで、ながーいヘビさんになろう!」
- 「静かにして!」 ではなく 「お口にチャックできるかな?」
子どもがパッとイメージできたり、思わず楽しくなっちゃうような言葉をつかうのがコツです。



「どんな言葉がいいかな?」と考えるのが、伝わる話し方の第一歩です!
短い文章で話す
大人は一度にたくさんの情報を処理できますが、子どもにとっては難しいもの。
「おもちゃを片付けて、手を洗ったら、イスに座ってね」と伝えても、子どもは最初の「おもちゃを片付けて」しか覚えていなかったりします。



話すときは、「一つずつ、短く区切る」が大切です!
- 「まず、おもちゃをおうち(箱)にバイバイしよう」
- (できたら)「すごい!じゃあ次は、おててをアワアワきれいにしよう」
- (できたら)「ピカピカだね!最後に、自分のイスに座ろうか」
一つひとつの行動を短い言葉で伝え、できたら褒める。
この繰り返しで、子どもは混乱することなく、次の行動に見通しを持つことができます。
伝える内容は事前にメモしておく
毎日の集まりやクラス全体に大切な話をするとき、活動の説明をするときなどは、事前準備をすると安心して話せます。
例えばこんな感じ。
- 導入(手遊びや歌など)
- 話す内容
- 話す順番
- 話が終わったらどうするか?
子どもたちが10人も20人もいると色々なことが起きるので、「バタバタしてたら伝えるのを忘れてしまった…」などを防ぐことができます。



メモがあれば心に余裕が生まれるので、落ち着いて話しやすくなりますよ!
ただ、メモばかり見るのではなく、子どもたちの顔や目を見て話すのが大切です。



長い文章だとメモから目が離せなくなります。
パッと見てわかるように、話す内容を短い単語にするのがおすすめです!
3つ目のコツは”トラブルへの対策”です。
保育のコツ③:トラブルとの向き合い方を知ろう


保育現場では、予想外のトラブルがよくあるものです。
「ひぇ、何も起きないで〜!」と思いますが、実はその経験こそが成長のチャンスなんです。
いろんなパターンを想定する
保育に「絶対」はありません。
だからこそ、事前に「こうなったら、こうしようかな」「こんなことが起きるかもしれないな」と、いろんなパターンを想定しておくことが大切です。
例えば、
- このおもちゃは取り合いになりそうだから、同じようなものをいくつか用意しておこう
- 集まりで子どもの集中が切れそうだから、伝えたいことをクイズ形式にしよう
- 雨で外に出られなかったら、このぬりえを出そう
など、事前に心の準備をしてと、いざというときスムーズに進めやすくなります。



経験が少ないと想定が難しいので、先輩に聞くのもおすすめですよ!
大きな声を出さずに子どもの姿を観察する



トラブルが起きると、つい「こらー!」「やめなさい!」と大きな声を出してしまいがちですよね。
そんなときはぐっとこらえて、子どもたちの姿をじっくり観察してみましょう。
- 危ないことは起きていないか?(安全の確保)
- 今、何が起きているのか?(現状の把握)
- この子たちは、本当は何がしたいんだろう?(意図の理解)



もちろん、ケガにつながる場合は、大声を出してでも止める必要があります。
何かあればすぐに止められるようにしつつ、その場の状況や子どもたちの様子を冷静に観察するのが、的確な対応への第一歩です。
周囲にヘルプを出す
自分1人ではどうにもならないこともあります。
そんなときは一緒に組んでいる先生や、周囲にいる他のクラスの先生たちに「手伝ってください!」と声をかけましょう。
- 子どもの勢いが強くて、一人では止められない
- トラブルに対応している間、クラスの他の子たちを見てもらう
- 大きなケガやお皿が割れたなど緊急事態



一人では無理!と思ったらすぐにヘルプを出すのが大切です。
次は「失敗との向き合い方」を解説します。
保育の「うまくいかない…」は成長のチャンス


ここまで具体的な方法をお伝えしてきましたが、一番大切なのは心の持ち方です。
先輩保育士も失敗の連続だった
今、あなたの周りにいる頼りがいのある先輩たちも、初めから何でもできたわけではありません。
みんな、あなたと同じようにたくさんの失敗を経験し、「どうすればよかったんだろう」と悩み、考えて、少しずつ経験を積み上げてきました。



あなたの隣りにいるしっかり者の先輩も、「わっはっは」と豪快な先輩もみんな同じなんです。
失敗するのが当たり前
若手でもベテランでも人間なので失敗します。
一人ひとり違った個性を持つ子どもたちが10人も20人も集まっているので、そう簡単にはうまくいかないものです。



だから、失敗するのは当たり前なんです。
でも、「失敗するのは当たり前なんだから、その中で何ができるか試してみよう」と、前向きに考えてみると、少し気持ちが楽になりませんか?



もちろん、子どもの命や安全に関わることは絶対に失敗できません!
安全管理を徹底した上で、子どもたちと一緒にたくさんの挑戦や失敗をくり返して、保育者と子どもが育ち合うのが保育の楽しさだと思います。
そもそも「失敗」って何だろう?
私たちが「失敗した」と感じるとき、もしかしたら「大人が思った通りに子どもを動かせなかったとき」かもしれません。
でも、保育って、大人の計画通りに子どもを動かすことではありませんよね。
- 子どもたちが夢中になって遊べる環境をつくる
- 子どもたちの学びが広がるような遊びを提案する
- そして何より、子どもと一緒に保育士もめいっぱい楽しむ
そう考えると、うまくいかなかったことも、実は「失敗」ではないのかもしれません。



ただ、子どもたちの興味・関心が、私たちの予想とは別のところにあっただけ。
「そっか、みんなは今こっちに夢中なんだね!」
「じゃあ、みんながやりたいことをもっと楽しめるように、先生は何ができるかな?」
子どもたちの「やりたい!」を探して一緒に楽しむ視点を持つこと。
それこそが保育の醍醐味であり、あなたの保育を豊かにしていくのではないでしょうか。



最後によくある質問をまとめるよ!
保育がうまくいかない若手保育士のよくある質問
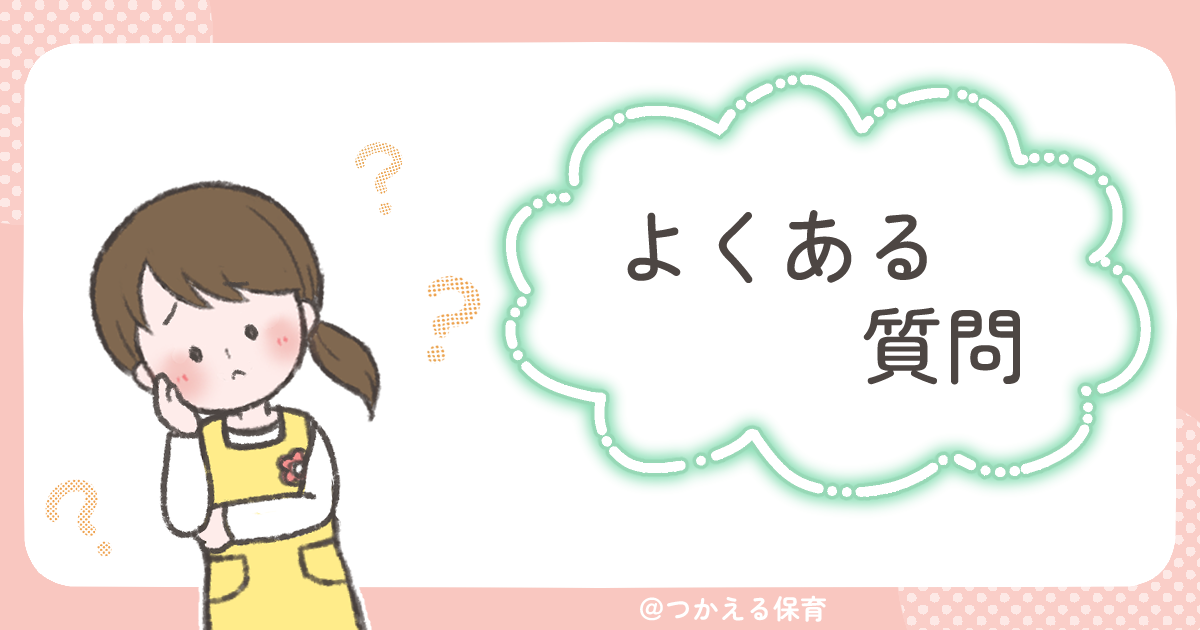
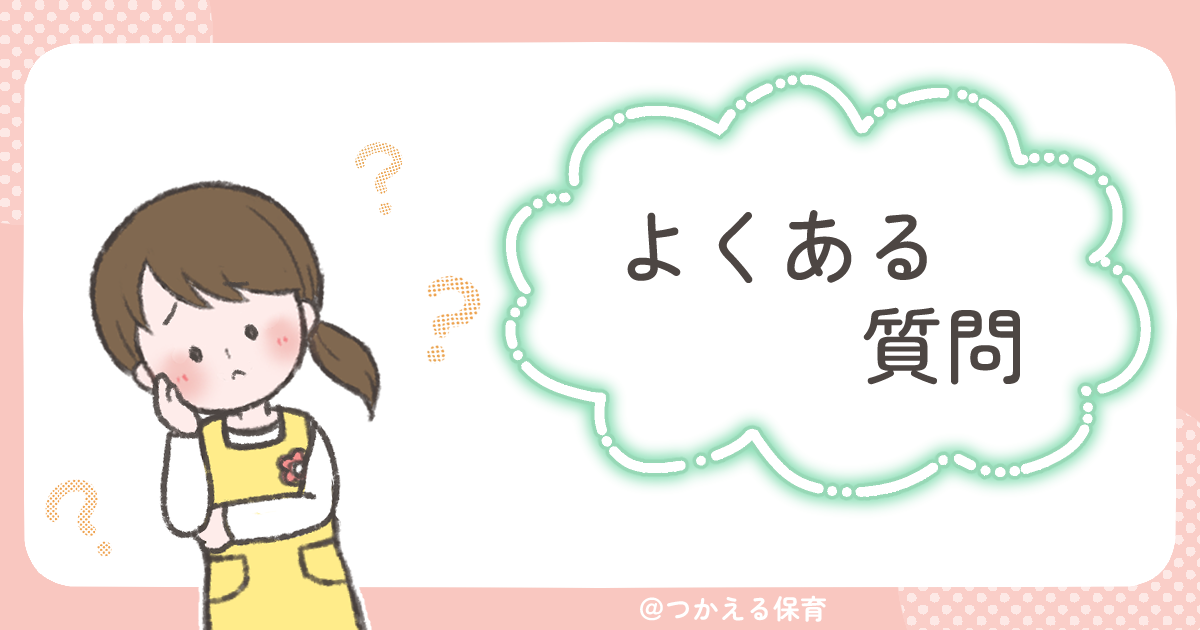
まとめ:保育がうまくいかないときこそ振り返ろう!
今回は、若手の先生が抱える「保育がうまくいかない」という悩みについて、その原因と具体的な解決策をお伝えしました。
- 集中力を引き出すには、まず信頼関係から
- 伝わる話し方は「短く・具体的に」
- トラブルは「うまくいかない場合の想定」と「子どもの観察」で乗り越える
- 「うまくいかない」は、自分を育てるチャンス
すぐに全てを完璧にこなす必要はありません。
まずは一つ、「これならできそう」と思うものから試してみてください。
そして、うまくいかなくても落ち込まずに、「なぜかな?」と振り返る。



その繰り返しが、あなただけの素敵な保育のスタイルを作っていきますよ!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が、あなたの明日からの保育のヒントになれば、本当に嬉しいです。
もしよろしければ、スケッチブックシアターの作り方など、他の記事ものぞいてみてくださいね。



現場で「つかえる」ネタがたくさんありますよ!
何かご質問や、「こんなことで悩んでる!」ということがあれば、お気軽にSNSからお声かけください。