特例制度で幼稚園教諭免許が取れるってどういうこと??



保育園で3年働いていたら、ちょっとの勉強とテストで幼稚園教諭免許が取れるんです!
みなさ~ん、今が大チャンスです!幼稚園教諭免許を取るために必要な時間と費用、勉強量が大幅に免除されていますよ~。
私もこの特例の期間中にひとがんばりして、6か月ほどで幼稚園教諭の資格を取りました!
特例制度のおかげで、働きながらでも試験に合格することができました。



しかも、このラッキーな期間が5年間延長されました!
令和12年3月31日まで幼保特例制度は続きますので、今年や来年などにゆっくりと勉強することができます。
ただ、特例制度のことは知っているけれど、パンフレットやHPを見てもなんだかよくわからなくて、なんとな~くスルーしている方もいらっしゃるのではないでしょうか?



“特例で幼稚園教諭免許を取る”ということを、体験談もふまえて、なるべくわかりやすくまとめました。参考にしていただけると、うれしいです。
幼稚園教諭免許を手にするまでの流れ


- 大学【申込み→勉強→試験合格】 → 教育委員会【申請→取得】
幼保特例制度で幼稚園教諭免許をとることをざっくり説明するなら、上記になります。
通信制大学などの説明を見ても、「科目修了試験に受かれば資格もらえるの?」「合格したら単位が認定されるってあるけど、それからどうするの?」などとモヤモヤしませんか?



ポイントは、試験合格(8単位取得する)までが大学とのやりとりで、それ以降の資格申請が教育委員会とのやりとりだということです。
ここがはっきりわかっていれば、全体像が見えてきます。
もう少し具体的に書きます。
- ■大学とのやりとり
-
- 自分の学習スタイルに合った大学に申し込む
- 講義を受ける(8単位ぶんの勉強をする)
- 試験を受けて合格する(8単位とる)
- 大学から証明書をもらう
- ■教育委員会とのやりとり
-
- 申請書類を自分でそろえる
- お住いの教育委員会に幼稚園教諭免許を申請する
- 教育委員会から免許をもらう
- ■大学とのやりとり
-
- 自分の学習スタイルに合った大学に申し込む
- 講義を受ける(8単位ぶんの勉強をする)
- 試験を受けて合格する(8単位とる)
- 大学から証明書をもらう
- ■教育委員会とのやりとり
-
- 申請書類を自分でそろえる
- お住いの教育委員会に幼稚園教諭免許を申請する
- 教育委員会から免許をもらう
ということです。
そして、①~④の“大学で単位を取る”という部分にかかる勉強量と費用の大幅な免除が特例制度なのです。
通常、大学に通えば数年の時間と何十万という費用がかかりますが、特例ならば6か月と6~8万円ほどですみます。
年に1度の教員資格認定試験を受ける手もありますが、とても難しく、合格率も20%ほどです。



特例ならば、ほぼ100%合格できると個人的には感じています。くわしくは、これから説明しますね!
まとめれば、今回の特例制度は本当にラッキーだということです。
さて、ものすごくざっくりですが、全体の流れをまとめました。次からは、特例制度や学習スタイルなどについて、くわしく説明していきます。
3つの条件をクリアすると特例を受けられる


- 保育士の資格を持っていること
- 保育士として3年かつ4320時間以上の実務経験があること
- その実務経験が特例制度の対象施設であること
3つの条件について、説明します。
① 保育士の資格を持っている
今現在、保育士として働いていなくても大丈夫です。
② 保育士として3年かつ4320時間以上の実務経験があること
今現在、この決められた時間を越えていなくても大丈夫です。
特例制度が終わりになる2030年3月31日までに、3年間かつ4320時間の勤務経験を満たせばOKです。
また、1つの施設で3年間働いてなくても大丈夫。いくつかの施設での仕事時間が、合計3年間かつ4320時間になればOKです。
③ その実務経験が特例制度の対象施設であること
実務経験として認められる施設は以下のとおりです。
- 保育所
- 認可外保育施設の一部
- 小規模保育事業(A型・B型)
- 事業所内保育事業(定員6人以上)
- 公立の認可外保育施設
- へき地保育所
- 幼稚園併設型認可外保育施設
- 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設 (1日に保育する乳幼児の数が6人以上)(認証保育所を含む)
- 幼稚園
- 認定こども園
*ただし、8は次の施設は除かれます。
- 施設を利用する児童の半数以上が一時預かりによる施設(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)
- 施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
- 定員が5人以下の施設
ご自分の職場が対象なのかどうかはっきりしない場合は、必ず勤務地の教育委員会・保育主管部局に相談することを強くおすすめします。



お金と時間を使って試験に合格しても、実は特例の対象でなかった・・となったら取り返しがつかないですものね。
各都道府県の教育委員会・教員免許担当部署の連絡先を下記の記事の中にまとめました。教育委員会への申請に必要なものや注意すべき点なども一緒にまとめていますので、ぜひ合わせてお読みください。



もしあなたが働いているところが幼保特例制度の対象でなかったら、別の場所に移ることも1つです。
念のため、あなたの転職をサポートしてくれる3つのサイトのリンクを置いておきますね。
✅保育士の転職でおすすめな転職サイト3選



ひとまず登録して、自分に合った保育園を探してみるのもいいですね。
次は、いつまでに学習をスタートさせるのがいいのかお知らせします。
2029年4月までには学習を始める


- 教育委員会への申請に、大きな落とし穴があります
まずは基本情報ですが、2030年3月31日まで(つまり2029年度末です)が特例制度の有効期間です。
この期間中に大学で8単位をとって(特例講座の試験に合格して)、お住いの都道府県の教育委員会に「幼稚園免許くださーい」と申請するのです。
しかし、この教育委員会に申請をするという部分に、実は落とし穴があるのです!
- 申請に必要な書類をそろえるのに1~2カ月かかる
- 都道府県によっては1月~3月くらいに申請受付が停止している!
これ、衝撃でした・・・・。
特例期間の最後にすべりこもうとしていたら、完全にアウトでした。



テストには合格しているのに幼稚園教諭免許がもらえない・・・という恐ろしいことが起こりうるのです。
では、そうならないためにはどうしたらいいのでしょうか?
- 2029年の4月までに学習をスタートさせ、9月までに試験に合格する
- 2029年の12月いっぱいまでに教育委員会に申請する
ということです。
まだまだ時間的余裕はありますが、教育委員会への申請について、事前に知っておいた方がその後スムーズだと思います。



「何が必要でどのくらい時間がかかるのか?」「申請を受け付けないのはいつか?」ということは確認が必要です。
下記の記事にまとめてありますので、ぜひ合わせてお読みください。
さぁ、それではいよいよ大学選びにいきましょう。
大学選びは3つの学習スタイルで決める
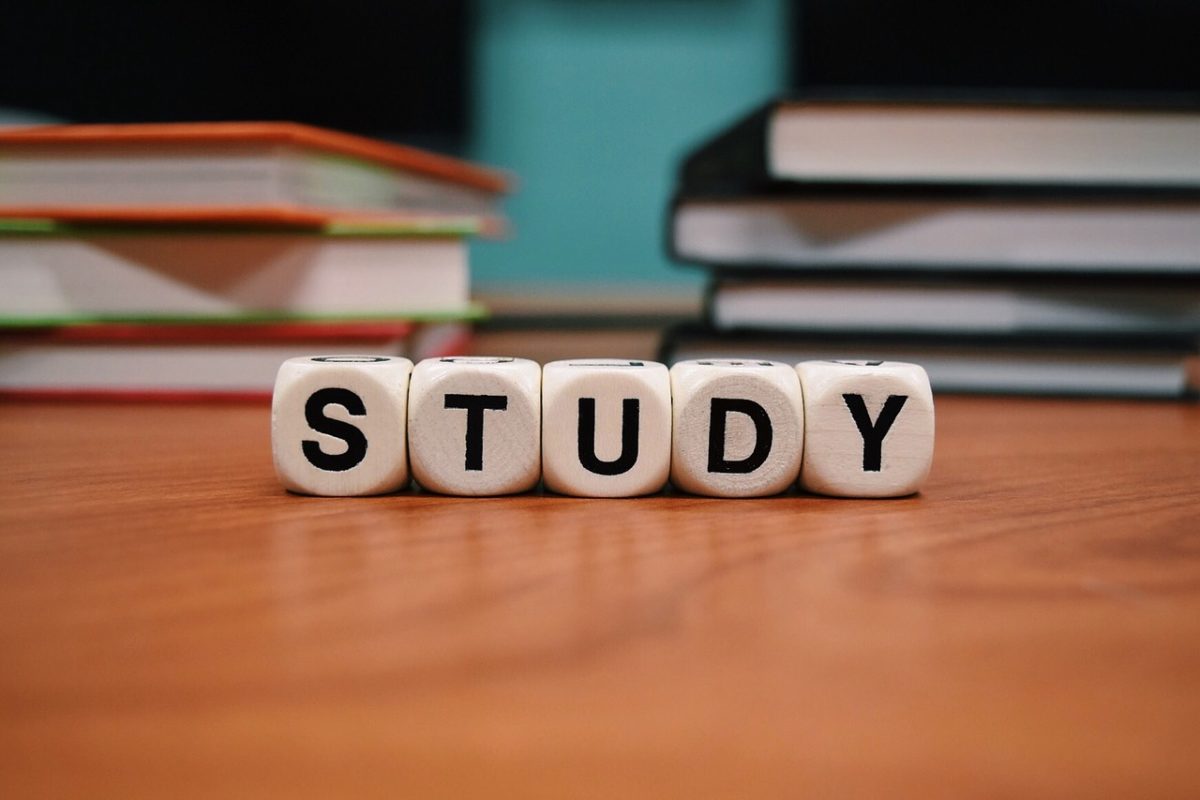
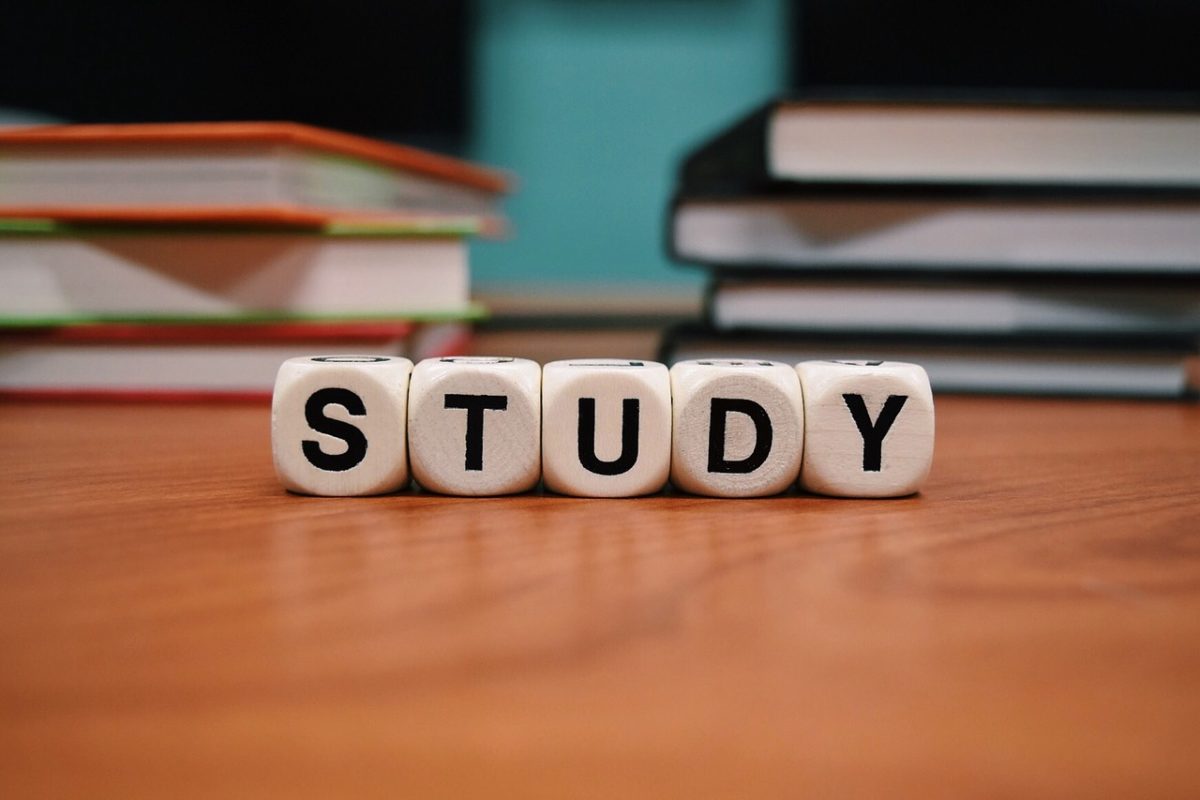
- 大学で講義を受けるか? パソコン・タブレット・スマホをつかって自宅でやるか?
現在、いくつもの大学が特例講座を開いています。



しかし、大学によって学習スタイルは異なります。
学習スタイルのちがいをひとことで言うと、
どこで勉強するのか?
どこで試験を受けるのか?
ということです。大きくわけて3つのタイプがあります。
- ■タイプA:大学で授業と試験を受ける
-
- 1日に4コマの授業というところが多い(1コマは1時間半)
- 土日や夏休み期間などに集中的に通う(4~6か月くらい)
- 試験は、授業の中で小テストやレポートのような簡易的なもの(予想)
- ■タイプB:ネットで授業、試験センターで試験を受ける
-
- オンライン授業(ネットで授業の動画を見る)
- スマホやタブレット、パソコンなどで授業を受けられる
- 家でも、通学の電車でも、好きな時に受講できる
- 小テストや試験は5択や6択の中から答えを選ぶマークシート方式
- 試験は、主要都市や大きな駅周辺の会場に行って受ける
- 合格まで、最短で3か月、通常で6か月、のんびりやって1年かかる
- ■タイプC:ネットで授業と試験を受ける
-
- オンライン授業(ネットで授業の動画を見る)
- スマホやタブレット、パソコンなどで授業を受けられる
- 家でも、通学の電車でも、好きな時に受講できる
- 試験はスマホやタブレットでは受けられず、パソコンのみで受けられる
- 試験を自宅で受けることができる
- 授業の動画を全て見て小テストやレポートを提出すると、その教科の試験を受けられる
- 小テストや試験は、5択や6択の中から答えを選ぶマークシート方式
- 合格まで、最短で3か月、通常で6か月、のんびりやって1年かかる
- ■タイプA:大学で授業と試験を受ける
-
- 1日に4コマの授業というところが多い(1コマは1時間半)
- 土日や夏休み期間などに集中的に通う(4~6か月くらい)
- 試験は、授業の中で小テストやレポートのような簡易的なもの(予想)
- ■タイプB:ネットで授業、試験センターで試験を受ける
-
- オンライン授業(ネットで授業の動画を見る)
- スマホやタブレット、パソコンなどで授業を受けられる
- 家でも、通学の電車でも、好きな時に受講できる
- 小テストや試験は5択や6択の中から答えを選ぶマークシート方式
- 試験は、主要都市や大きな駅周辺の会場に行って受ける
- 合格まで、最短で3か月、通常で6か月、のんびりやって1年かかる
- ■タイプC:ネットで授業と試験を受ける
-
- オンライン授業(ネットで授業の動画を見る)
- スマホやタブレット、パソコンなどで授業を受けられる
- 家でも、通学の電車でも、好きな時に受講できる
- 試験はスマホやタブレットでは受けられず、パソコンのみで受けられる
- 試験を自宅で受けることができる
- 授業の動画を全て見て小テストやレポートを提出すると、その教科の試験を受けられる
- 小テストや試験は、5択や6択の中から答えを選ぶマークシート方式
- 合格まで、最短で3か月、通常で6か月、のんびりやって1年かかる
かなりざっくりと、それぞれの特色をまとめました。
働きながら、子育てをしながら、という方も多いと思います。だから、在宅ですべてできるのか、それとも、外に行かなくてはいけないのか、というのは大きなポイントですよね。



それぞれの生活スタイル似合わせて、「どんな状況なら勉強しやすいのか?」を考えて選んでください。
ちなみに、私はタイプC“すべて在宅スタイル”の日本福祉大学を選びました。仕事や子育てがあるので、なかなか家を離れられないからです。
子どもが寝てからの時間や、週末の時間を利用して6か月で合格しました。
実際にやってみてわかったことや、勉強時間をぐっと縮める効率的なやり方、試験の傾向、合格までにかかる時間など、下記の記事にまとめてあります。



ぜひ合わせてお読みください。
大学探しに便利な“一覧表”がある


- 文部科学省が作成した「一覧表」を見よう!
もう答えを言ってしまっていますが、文部科学省のサイトには、特例講座をやっている全国の大学の一覧表をダウンロードできるページがあります。



それを見ればどんな大学があるのかざっとわかりますし、その大学が通学コースなのか、通信コースなのかもだいたいわかります。
お値段ものっているので、簡単に比較できるところも便利です。まずはこちらから目を通して良さそうなところを探し、大学HPのリンクからさらに調べるということができます。
こちらをクリックするとダウンロードできますよ!
次は、“おすすめの大学”を紹介します。
おすすめの大学はたった1つ!


- おすすめは、“通学一切なし!”“値段が1番安い!”の日本福祉大学です。
またしても答えを言ってしまっているので、あとはこの大学のHPに飛ぶだけです。
でも、とりあえず理由も書きますね。
日本福祉大学がおすすめな理由



私は日本福祉大学で幼稚園教諭免許の試験に合格しました。
やってみて感じたのは、「1番かんたんに合格できるのは、ネットで授業と試験を受けられるタイプの大学だな」ということでした。
なぜなら、試験中に教科書や自分でまとめたものを参考にできるからです。これは決してズルをしているのではありません。



試験の意味合いが、“学んだことを再確認する”という程度なのだと私は考えています。
大学からも「試験中に教科書を見てはダメ」というような注意もないです。このあたりが“特例”らしいところでしょうか。
また、すべて自宅でできるので、通学などの無駄な時間が一切ありません。働きながら、子育てしながら、自分のペースで勉強できるところは大きなメリットです。



ひかえめに言って最高ですね。
勉強も試験もすべて自宅でできる大学は2つのみ。
はい、決まりですね!
ただ、例外ケースが3つあります。
例外①:とにかく費用を安くしたい方
「なるべく安く済ませたい」という方は、以下の2つの学校がおすすめです。
勉強は自宅・試験は会場に行くスタイルとなります。
例外②:出身校の割引を使いたい方
卒業生割引というものがあります。



どの大学にもあるわけではないのですが、出身校を調べる価値はありますね。
例外③:試験に受かる自信がない方
試験に不安が強い方は大学に通って授業と試験を受けるタイプを選ぶのがいいと思います。
理由は最後まで授業を受ければ(たぶん)単位がもらえるからです。



実際に私は受けていないので“たぶん”としか書けなくてすみません。
しかし、4~5ヶ月も土日に通わせといて、「試験に落ちたからもう1回受講してね♡」などと言わないですよね。
だって、家で参考資料見ながらテストを受けられる大学もあるのですよ!?
ということは試験はあっても、レポートや小テストといった形で授業中に行うくらいかなと予想します。



気になる方は実際に大学に問い合わせてみてください。
では、次は勉強する科目についてです。
どんな勉強をするの?


- 5科目8単位が基本です
実際にどんな勉強をするのか簡単にお知らせします。



選ぶ大学によって科目名は少しずつ異なるのですが、中身に大差はないと思います。
たとえば、私が実際に受講した日本福祉大学(通信)では以下のような科目名です。
- 教職入門(2単位)
- 教育制度論(2単位)
- 保育課程論(1単位)
- 保育内容と方法(2単位)
- 幼児理解の理論と方法(1単位)
このように、特例制度では「8単位・5科目」の授業を受けます。



1科目につき1つの試験があり、全ての試験に合格すると、教育委員会に幼稚園教諭免許を申請することができます。
さぁ、次は「育児や仕事をしながらでも勉強できるのかな?」という疑問にお答えします。
子育て中や働きながらでも合格できるの?
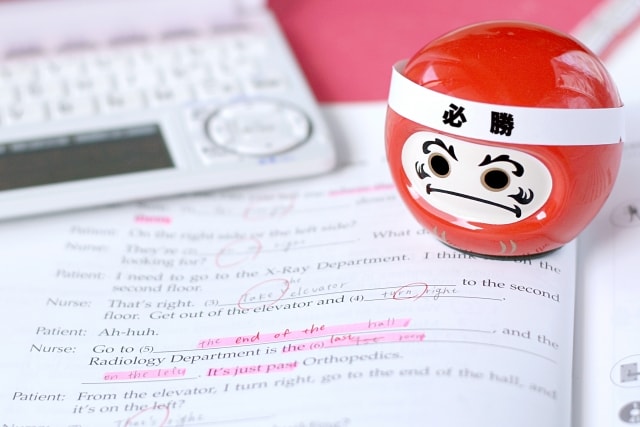
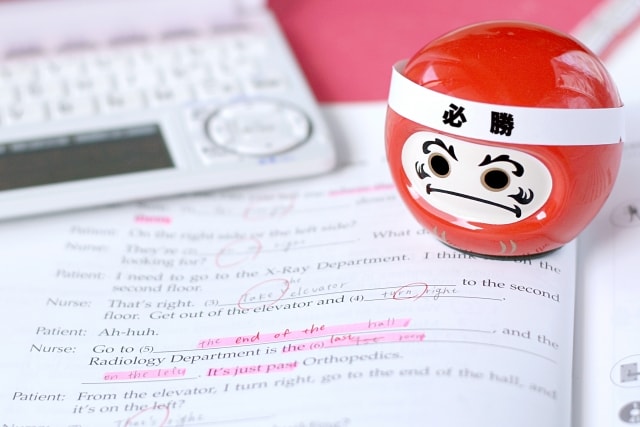
- 勉強も試験もすべて自宅”の学習スタイルが合格への近道です
子育て中だったり仕事をしている方は、
「自分の時間だってなかなか取れないのに、勉強できるのだろうか?」
「勉強する時間がないのに、試験に合格できるかな?」
という疑問が当然あると思います。
私も働きながらでしたが、6か月で合格することができました。



実際にやってみてわかったのは、自分に合った学習スタイルを選べば可能ということです。
1番の安全策は、大学に通って講義を受ける学習スタイル。通常の大学のように、通っていれば単位がもらえるようです。(簡単な小テストやレポートはあるでしょうが)
でも、何か月ものあいだ、土日に大学へ通うのは難しいですよね。
だから、選ぶのは“勉強も試験もすべて自宅”の学習スタイルです。



私は日本福祉大学の“勉強も試験もすべて自宅”スタイルを選びました。
参考までに、具体的な中身を少し書き出します。(2018年の情報です)
- 学習方法は【スマホやタブレットで講義の動画を見る】
- 1つの講義動画は10~30分程度
- 育児のすきま時間でも、通勤時間でも見られる
- 1週間で4時間ほどの勉強×4カ月で合格
- テストは細かいことを暗記する必要はなく、保育の経験があれば答えられる問題も多い
- テストは教科書を見ながらできる
という感じです。
1週間で4時間の勉強でいいならば、できそうだと思いませんか?
ただ、中には、日々の仕事や子育てが激務で・・という方もいらっしゃるかと思います。その場合は、6か月ではなく1年というスパンで勉強計画を立てればいいと思います。



そうすれば、1週間で2時間の勉強を、計8か月やればOKです。
ただ、ここまで読んでも実際に受けてない方にとってはよくわからないかもしれません。ですので、日本福祉大学で幼稚園教諭免許をとる方法をまとめました。
時間を短縮させて勉強するウラ技や、日本福祉大学の特徴、勉強や試験対策、注意点などをまとめてありますので、ぜひ合わせてお読みください。



そうはいっても仕事から帰ると時間も体力もなくて、働きながら勉強するなんてムリそうです…。



保育の仕事って本当に大変ですよね。私も保育士なのでそのお気持ちはわかります。
ただ、もしかしたら、あなたの園の職場環境がほかよりハードなのかもしれません。



えっ、どういうことですか?



最近は残業や行事がほとんどなく、現場の保育士の負担を減らしている保育園が増えてきています。
あなたが希望する働き方や保育観に合った園を探してみることも、1つの方法かもしれませんよ。
おすすめの転職サイトを紹介しますので、もしよろしければ見てみてください。
✅保育士の転職でおすすめな転職サイト3選
今ある人間関係や目の前のかわいい子どもたちと離れるのは簡単ではありませんが、あなたのこころや身体が大事にされるような職場を選ぶのも大切なことだと思います。



迷うなら、ひとまず行動して、動きながら考えましょう!
次は、いきなりそもそも論。
「本当に幼稚園教諭免許はとらなきゃいけないのかなぁ・・」にお答えします。
幼稚園教諭免許って本当に必要なの?


- 保育士と幼稚園免許の両方がないと幼児クラスの担任になれない時代が来るかもしれません
保育業界にも新しい波が来ています。
✅【平成30年(2018)4月】新しい保育指針がスタート・3法令の同時改訂
- 幼稚園教育要領
- 保育所保育指針
- 幼保連携型認定こども園教育・保育要領
*3法令の同時改訂により、9時~13時の間は、どの施設であっても一定以上の質をもった幼児教育を行うことになっています。



今は“特例期間”という移行期だから大きな変化を感じないかもしれません。
しかし、“保育士+幼稚園免許”を持つ保育者が一定数になって“特例期間”が終了したときはどうでしょうか?
9時~13時が幼児教育の時間だから、幼児クラス(3~5歳児クラス)は両方の資格を持っている【保育教諭】しか保育できないということになってもおかしくないと思います。
また、今後少子化がさらに深刻になっていきます。その時には、都心部でさえ保育園は定員割れを起こし、保育園も、幼稚園も、共にこども園になるでしょう。



そこでは【保育教諭】(保育士+幼稚園教諭)が求められることになります。
この数年では変わらなくても、10年、20年の単位では大きな変化が待っているように感じます。ですので、今の20・30代は特に幼稚園教諭免許の取得が必要かと私は思っています。
そうは言っても、
「まぁ、今がチャンスなのはわかったけどさぁ・・」
「なんかめんどくさいなぁ。なくても困らないんじゃない?」
と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、せっかく今、国の政策として“特例期間”があるので、その大きな波に乗った方が後々楽なのではないでしょうか?
具体的に言えば、
- 最低限のお金や時間で幼稚園免許がとれるチャンス(試験も易しい)
- 幼稚園教諭免許を持ってないことで職場に迷惑をかけないようにする
- 幼児クラスが持てなくなったら自分のキャリアが狭くなる
- 自分の保育園がこども園になっても大丈夫
という感じでしょうか。



先のことはわかりませんが、幼稚園教諭免許があったほうが安心なのは事実だと思います。
特例期間は「安く・短期間・簡単に」取れるので「やっぱりとろう!」と私は思いました。
みなさんはどう考えますか?
最後に


最後に、少しだけ説明を付け足させてください。



この記事では複雑なことをあえて単純に書いています。
それは、“わかりにくいから行動に移せていない”という人の助けになればと思うからです。
ただ、“資格を取る”という大事なことなので、こまかい部分やはっきりしない点については、お住いの都道府県の教育委員会に必ず確認をしていただくようお願いします。
いそがしい毎日のなか、ちょっとした時間で大事な部分をパッとわかっていただければ・・と思っています。



この記事がみなさまの考える材料になれば嬉しいです!
長い文章を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
✅幼保特例制度の役立つ情報まとめ
- 【ここからが大変!】試験に合格したらやること(解説記事はこちら)
- 【幼保特例2020年度版】おすすめの通信制大学はこの2つ!(解説記事はこちら)
- 【そんなの知らなかった…】教員免許が失効していると幼稚園教諭免許を取得しても失効になる話(解説記事はこちら)


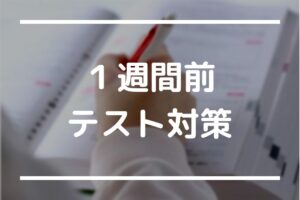

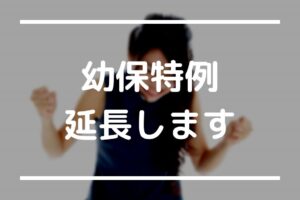
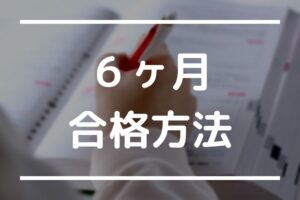
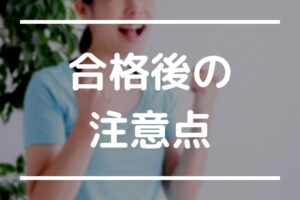
コメント
コメント一覧 (33件)
わかりやすい内容ありがとうございます。実は去年9月に保育士として復帰しているものです。幼稚園免許はもっておらず、20年程前に2年 正規で保育士をしていました。
32年3月には無理だと諦めていましたが、延長されるならチャレンジしたいです。他の方も法案が通るのはきわめて高いとおっしゃっているのですが、まだ確定ではなく不安で、大学に通うのもためらっています。どのくらいの可能性があるのかご存知のことで大丈夫ですので教えて頂きたいです。
西村さま
コメントありがとうございます!
以前保育士として働いていて、現在は復帰なされたのですね。
復帰して半年以上たち、ほっと一息といったところでしょうか。
そして、幼保特例制度が延期されるかどうかを心配されているとのこと。
私自身もただの保育士なので、何か確かなことを知っているわけではありません。
ただ、
現在、国策として“幼保連携型認定こども園”を増やしていることや、
そのためには保育士も幼稚園教諭免許も両方持っている“保育教諭”を増産しなくてはいけないこともあり、
たった5年間で幼保特例制度を終了させないのでは?と思っていました。
そこにきて、
子ども・子育て会議で期間延長の方向で意見がまとまったというニュースがあり、
これは決定しそうだなと思い、記事もアップした次第です。
まぁ、本当にただの保育士なので、すべて想像なのですが(-_-;)
はっきりしたお応えができずにすみません。
西村さまの状況からすると、
期間延長にかかわらず、
この春から初夏にかけて勉強を開始すれば、時間的には資格取得が間に合うかと思います。
あとは、ご自身の状況次第でしょうか。
時間と費用に余裕があれば、日本福祉大学の通信をおすすめします。
勉強もテストもすべて自宅でできますから。(PCがあれば)
さて、明日から4月。
新入園児が入ってきて、保育園は賑やかになりますね。
ここから子どもも大人もひと頑張りのシーズン。
お体に気をつけてお仕事されてくださいね。
私も今年は幼児クラス。
がんばりま~す(*^^*)
説明で良くわかりました、ただ
最終試験に、合格できるのか
不安何です
福原さん
コメントありがとうございます。
福原さんがおっしゃる通り、この幼保特例試験は実際に試験を受けてみないと、本当に不安なんですよね。
私も同じでした。
本当に受かるのかな?
半年で終わるかな?
働きながらなのに、勉強できるかな?
とドキドキしていました。
結果的には、個人的な感覚ですが、思ったほど難しくなかったし、
むしろ、幼保両方の資格を持つ人を増やしたいという大きなねらいがあるので、
かなり合格しやすくしているのだと思いました。
それは、試験も家のPCでできてしまうことや、
大学で行われている2カ月くらいの短期集中講座に出ればOKというやり方にも表れていると思います。
幼稚園教諭免許は文部科学省が管轄する学校の教員免許です。
監督官のいない、自宅で受ける試験で合格できるなんて、普通は考えられないと私は思います。
その考えれない状況が“特例”なのでしょう。
今がチャンスなのです。
実際に勉強したり試験を受けてないとどうしても不安になると思いますが、
今だけのチャンスというのは、受けてみた者としての正直な感想です。
福原さんの背中を押すには不足だとは思いますが、
私が言えるのはこのくらいになります。
どうぞ、ご検討ください。
そして、何かお困りのことがあればいつでもコメントくださいね!
それでは。
カモネギさん、ありがとうございました。50代パート保育士です。6月から始めて猛スピードで勉強し全教科受験までこぎつけました。何回も、ブログを読んで参考にしました。お仕事されながらブログ作成、すごいですね。沢山文章打てないのですが短いですが、本当に感謝しています。ありがとうございました。
ぱおさん
コメントありがとうございます。
6月からの2カ月で全教科受験までいきつくとは、そうとう努力されましたね!
仕事や家事の合間を縫ってがんばられたのが目に浮かびます。
本当にお疲れさまでした。
試験は土日に始まり、次の土日も…ということになりますね。
続けての試験になりますが、ここまできたら全試験クリアを目指してくださいね!
試験を始める前のあのドキドキ、思いだしました。
試験を受ける前に子どもたちに部屋に入らないことを伝え、
途中で入ってこないか?などと変なドキドキもありつつ受験していました。
ぱおさんの受験環境はいかがでしょうか。
朗報をお待ちしていますね(*^^*)
そして、ぱおさんの感謝の言葉。
文の長短ではなく、気持ちが伝わってきました。
本当に嬉しいです。
こちらこそありがとうございます。
この連休は子どもと出かけたり、ちょっと一休みしたりして返信が遅くなりました。
でも、その間にぱおさんをはじめ、みなさんから嬉しいお言葉をいただき、気持ちが奮い立っていました。
また、がんばっていこうと思えました!!
少しずつブログを広げていきますね~。
それでは、また。
はじめまして!
2011年に合格率20%の特例制度試験に見事惨敗した者です(^^;
それから結婚出産を経て、2017年にパート保育士として復帰しまして…
最近、幼稚園教諭の免許の特例制度で免許を取った!(大学に通って)と言う事を同じ職場の40代パート保育士さんに聞き^ ^
えーーーー!
大学に通って免許取れるの?
と、びっくりして調べた所^ ^
かもねぎさんのサイトに辿りつきました!
5年延長された事も知り、これは運命かも!と思い、頑張ってみる決意をしました^ ^
8年前に実務証明をしてもらった経験があるのでクリアしているし、日本福祉大学に入る為の書類を時間をかけて集めなくて良いみたいなので頑張ってみようと思います。
かもねぎさんや、日本福祉大学の事を知ったのは昨日の事で…
ここまで心を動かされると言う事は、幼稚園教諭免許のない自分がずっとコンプレックスに感じていたからだと真摯に受け止めています(;_;)
だったら、今年中にケリつけたる!!という意気込みで、ギリギリですが願書を今月中に出そうと思っています^ ^
かもねぎさんの記事は私みたいな人の心を動かすかなりの力を持っています!
出会えて良かったです^ ^
ありがとうございます!
不安はありますが、家事子育て仕事の合間に頑張ってみます!
まーちゃんさん
がんばって記事を書いてよかったなと心底思いました。
誰かの役に立てば…と思って書いていましたが、本当に報われたなぁと感じています。
お忙しい中、わざわざ色々と書いていただき、こちらこそ感謝です。
ありがとうございます。
さらにこの『つかえる保育』ブログを大きく育てていきたいと思いました。
ちょっとずつですが。
そして、昨日このサイトを見て、特例制度を受けることを決意されたとのこと。
ご自分の心の奥にあった気持ちにも気づかれたのですね。
物事が起こったときに、パッと判断して行動に移すことがやはり大事ですよね。
そこに乗るか乗らないか。
人生の分岐点。
私もあーちゃんさんのように、ここぞというときはすぐに行動したいと思っています。
一見大変のように見えますが、自分から1歩踏み出すと、わくわくする人生が待っていると考えます。
そうなると“大変”ではなく、“楽しい”になります。
そして今、“楽しい”という思いでこのブログも書き進めています。
1つの記事に何時間もかかりますが、毎日ちょっとずつ出来上がっていくのが楽しいです。
あーちゃんさんも8月いっぱいに申請し、そこから勉強スタート!
子育てに家事に仕事にと、ご自分の中でいいバランスをつくるまでひと頑張りだと思いますが、
充実した日々が待っていると思います。
お困りの時やくたびれた時などにはまたぜひコメントください(*^^*)
一緒にがんばりましょうね!!!
ご無沙汰しております。
日本福祉大学にて無事に単位を取得し、令和2年2月29日に幼稚園2種免許が届きましたーーーーーー‼︎
知識を分けて下さり、私の心を動かして下さった、かもねぎさんに報告したくてコメントさせて頂きました^ ^
短大でほぼ単位を取っていた事もあり、日本福祉大学では教育制度の2単位のみの取得で大丈夫でした!
短大時代に実習で挫けてしまいましたが、勉強だけはしておいた自分にも感謝している所です♡
私も晴れて、保育教諭となる事ができました!
力を分けて下さり本当にありがとうございました‼︎
今はコロナウイルスの影響でとても大変な時期ですね…
何だか、ふに落ちない気持ちもありますが…
お互い体調に気をつけて、過ごしましょうね。
まーちゃんさん
幼稚園2種免許の取得、おめでとうございます!
仕事に子育てにとお忙しい中で勉強するのは並大抵のことではなかったと思います。
本当にお疲れさまでした。
短大時代の自分に「ありがとー(*^^*)」と言ってあげたいですね!
コロナコロナという時に、ステキなご報告を聞くことができて嬉しい限りです。
私もまーちゃんさんの頑張りから力をもらいました。
ありがとうございます。
様々なことが起きていますが、体に気をつけて過ごしたいですね。
そして、お互いに仕事に子育てにとがんばりましょうね♪
私にとって、知りたいことが存分に載っていて、
本当にありがたいです!勇気と希望が湧いてきました。
お忙しいのに恐縮ですが、
もし、ご存知でしたら、教えて頂きたいのですが…
わたしは、保育士3年目のパートで、
週に2~3日程の勤務なので、
今のところ、4320時間の勤務には到底満たしておりません。4月から新しい職場の幼保連携型認定こども園に変わる予定でいまして、そちらの園長先生に、「幼稚園教諭取得を」と言われ、わたしも前向きにその方向で考えているのですが…。
2024年度末までの特例とのことで、まだ期間があるので希望を持っているのですが、
①まだ、4320時間を満たすまでに、しばらくの月日がかかりそうなのに(見込みなのに) 先に幼稚園教諭取得しておいても大丈夫でしょうか?つまり、取得今年仮にできたとしても、教育委員会への申請が、2024年頃になっても問題はないでしょうか?
なーたんまんさん
コメントありがとうございます。
4320時間という規定の時間に今は満たないけど、あと数年でクリアできる。
その見込みのまま、幼保特例制度で幼稚園教諭免許をとりたいけど大丈夫か?というご質問ですよね。
結論からお伝えすると、【可能】であると思います。
同じような質問が「日本福祉大学」の幼保特例のページのQ&Aにあったので、該当の部分を抜粋します。
『Q:実務経験が2年しかありませんが、先に必要な単位を修得しておき、3年かつ4,320時間以上の勤務経験を満たした時点で申請をしたいと考えていますが可能でしょうか?
A:可能です。予め単位修得していただき、実務経験年数などの要件を満たした時点で申請ください。なお、本特例制度は2025年3月までの期間限定の制度となっていますので、2025年3月までに申請する必要があります。ご注意ください。』
以上、抜粋でした。
(https://www.nfu.ne.jp/youho_tokurei/faq/index.html リンクをつけたのでご確認ください)
そして、確認ポイントはが2つ。
①大学と教育委員会からもらうものはそれぞれ違います
・大学からは、勉強・試験を通して、特例で幼稚園教諭免許をとるために必要な【8単位】をもらう
・教育委員会からは、書類をそろえて申請をすることで【幼稚園教諭免許】をもらう
②【3年かつ4,320時間以上の勤務経験】という基準を遅くても2024年の夏までにクリアする
・2025年1月以降は、教育委員会が申請を受け付けない期間が存在する
・2024年9月から教育委員会への申請準備をすれば十分間に合う
①は念のための確認です。
ただでさえややこしい幼保特例制度なので、頭の中を整理させましょう。
②については、こちらの記事でもまとめてあります。https://tukaeru-hoiku.info/tokurei-sinsei/
(もうご覧になったかもしれませんが)
なーたんまんさんは、“保育士3年目・週に2~3日程の勤務”とのことなので、2024年まではかからないと思いますが、やはり念のため確認でした。
いかがでしょうか?
これでお悩みは解決できましたか?
ただ、これは一個人である“かもねぎ”と一教育機関である“日本福祉大学”がいっていることです。
ルールを決めている“教育委員会”が言っていることではありません。
なーたんまんさんの人生を決める大切なことなので、
ぜひご自身でお住いの都道府県の教育委員会にTELで確認することを強くおすすめします。
最善を尽くしてステップアップを図り、保育園の子どもや職員方と楽しく働けることを、
同じ保育士として願っております。
何かご不明な点がございましたら、またいつでもコメントくださいね(*^^*)
それでは~。
こんばんわ。こちらのブログを参考にしながら、6月に修了試験に臨む者です。毎日試験勉強しながら、受かるかな?と不安でいっぱいです。とにかく小テストを何回も何回も解いて繰り返しているのですが、こんな感じでいいのでしょうか…。
何かいい勉強法があれば教えていただきたいです。
cocoさん
コメントありがとうございます。
6月の試験まで1カ月ちょっとですね。
私も実際に試験を受けるまでは「本当に合格するのかなぁ」と不安だったので、
cocoさんのご心配はよくわかります。
しかし、テストの内容が小テストの問題と同じものが多いことや、
質問の仕方がちがうだけのものが多いことに安心しました。
(3年前の情報ですが…)
ですので試験対策は2つ。
1.小テストを繰り返しやって理解する
2.小テストの内容が教科書の何ページにあるか目次をつくっておく
これをやっておいたので、どの試験も1発で合格することができました。
一度試験を経験するまではドキドキするとは思いますが、
どうぞ頑張ってくださいね!
何か困ったことがあればいつでもコメントください。
同じ試験を受けるものとして、応援しております(*^^*)
こんばんわ。以前、こちらで試験に対する相談をさせてもらったcocoです。今日、試験の結果が出まして、無事に全科目合格していました。こちらで、勉強方法や、みなさんの情報を参考にさせてもらったおかげだと思います。ありがとうございます。
あとは、実務経験がまだ足りないので、頑張りたいと思います。こちらのブログに辿り着けて救われました。本当にありがとうございました。
cocoさん
合格おめでとうございます!!
短い勉強期間で、ばっちりの1発合格。
本当にすごいです。
たくさんの不安を乗り越えて自力で最後までやりぬいたこと、
これからの大きな自信になりますね。
実務経験がまだ足りないとのことですが、この経験は大きいです。
実務経験は時間の問題です。誰でも通る道です。
しかし、cocoさんが努力したこと、磨いた力は、誰でもできることではありません。
保育園でのお仕事は“保育”だけではないですよね。
文章力やコミュニケーション力、論理的思考などいろいろなものが必要です。
cocoさんのような“努力できる力”も魅力的な能力の1つです。
ぜひそのお力を、周囲の子どもや大人が笑顔になることにつなげてください。
勝手ながら、私はそんなことを思いました。
長文になってしまいましたが、本当におめでとうございます。
とっても嬉しいです。
また、いつでも遊びに来てくださいね(*^^*)
それでは。
興味深く読ませていただきました。
とても参考になります。ありがとうございます☆
一つ質問よろしいつでしょうか?
私はこれから保育士の資格をとろうとしているのですが、3年間の実務経験は保育士としての3年間でないとダメなのでしょうか? 無資格状態での実務ではカウントに入らないのでしょうか?
もしご存知でしたら教えていただきたいです。
宜しくお願い致します!
えりさん
コメントありがとうございます。
えりさんの参考になっているとのこと、とてもうれしいです。
保育士も幼稚園教諭もとにかく忙しい仕事ですよね。
私が情報をまとめることで、少しでもみなさんの時間短縮ができたらと思っています。
さて、えりさんは幼保特例制度で保育士の資格を取ろうとされているのであっていますか?
ひとまず解説すると…
【幼保特例制度】
・保育士として3年間働いたら、特例で幼稚園教諭免許の試験に挑戦できる
・幼稚園教諭として3年間働いたら、特例で保育士の試験に挑戦できる
ということだと思います。
ですので、えりさんが幼稚園教諭として3年間働いていたら(見込みでもOK)、この特例にも参加できます。
もし、えりさんの状況がちがっていたらごめんなさい。
また、いつでもお声かけくださいね(*^^*)
ありがとうございました!
わかりやすい説明、ありがとうございました。
実務経験が4320時間あるか怪しいのです。
まずは
何からやったら良いでしょうか…
転勤族で勤務した保育園は5ヶ所ほどあり、全部パートです。
今は免許なしで幼稚園で働いています。
福田さん
コメントありがとうございます。
記事が参考になったようで、私も嬉しいです。
福田さんは今まで5つの保育園でお仕事をされてきたのですね、
新しいところに慣れるために様々なご苦労があったかと思います。
その一方で、色々な保育園で保育をしてきた、というのは貴重な経験ですね。
保育は答えが1つではなく、園によって、人によって、かなりちがうことも多いですよね。
今まで見てきたこと、感じてきたことが、福田さんの中で力になっているのではないでしょうか?
さて、幼保特例に関しては、どのような手順で進めればいいかとお悩みのようですね。
私なりにちょっと考えてみました。
とにもかくにも大切なのは【幼保特例を受ける資格があるか】ということです。
つまり、【保育士資格をもって保育園で保育をしてきた時間が4320時間あるか】です。
これを確認するには面倒ではありますが、福田さんが今まで務めてきた保育園に勤務時間を尋ねることです。
1つ1つの園に電話(もしくは手紙)をして、幼保特例を受けたいから、とお願いすることが先決かと思います。
あとは、各園での勤務時間の合計が4320時間を超えているかですよね。
ちなみに、以下は文部科学省の【幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A】というページから、関連する箇所を抜粋しました。
( https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339608.htm より)
3-9.在職年数は直近のものでなくとも可能か。また、複数の機関での勤務経験を通算することは可能か。
(答)
直近のものでなくとも可能です。また、複数の機関での勤務経験の通算も可能です。その場合、それぞれの施設における実務証明書が必要になります。
3-10.本特例制度が施行される前の在職年数や基礎資格を取得する前の在職年数は認められるのか。
(答)
本特例制度の施行の前の在職年数は認められますが、基礎資格を取得する前の在職年数は認められません。
3-11.廃止や統合された施設における在職年数はどう証明したらよいか。
(答)
施設が廃止された場合でも当該施設の設置者が存在している場合は、当該施設の設置者に証明をしてもらってください。施設の設置者が存在していない場合であっても、統合等によって必要書類等が引き継がれており、引き継いだ団体が証明できる場合は引き継いだ団体による証明も可能とします。
長くなりましたが、つまり、複数の園の勤務時間の合算OK、しかも、それぞれの施設から実務証明書をもらう必要あり!ということですね。
勤務時間+実務証明書
この2つを今まで勤務してきた保育園にお願いするのが、1番先にやることです。
今年度の幼保特例の募集は終わっていますが、12月からまた次年度の募集が始まっていきます。
私がオススメする日本福祉大学も12月からです。
結果がどうなるかわかりませんが、今、行動するのがよいかと思います。
資格がなくても幼稚園で働くことはできますが、やはりあった方がご自分でももっと自信を持てるのではないでしょうか?
通常では考えられないほど幼稚園教諭免許を取得するハードルが下がっている幼保特例制度なので、
絶対に今がチャンスです!
まずは、保育園に連絡をするところから始めてみませんか?
もし何かあれば、またいつでもコメントしてくださいね~(^^)/
それでは。
丁寧なご返信を頂き、ありがとうございました。各園から実務経験の証明書を書いてもらいました。時間数を満たしていると思うので(園によって記入の仕方が違っていたので、はっきりした時間数が分からない園も)これから日本福祉大学に願書を出そうと思います❗本当にありがとうございました
福田さん
ご返信ありがとうございます。
すでに動かれていたのですね!
行動が早いです(*^^*)
ひとまず各園から証明書をもらえたとのこと、本当に良かったです。
これで日本福祉大学の申し込みも目の前ですね。
あと、これは念のためですが、お住いの都道府県の教育委員会に確認をしたほうがいいかと思います。
手持ちの証明書とそこに書いてある時間数を伝えて、これで特例の資格があるかどうか確認することをおすすめします。
時間数が明らかに超えていたとしても、念のため。
手間が1つ増えてしまいますが、福田さんの大事な時間とお金、労力を無駄にしないためです。
時間数がクリアになり、無事に日本福祉大学に入れますように!
それでは、また~。
とても興味深い記事をありがとうございます。
おうかがいしたいのですが、今現在育休中で、職場職種は私立の認定こども園の事務職です。
(育休は2021年8月末まで取得予定)
幼稚園教諭、保育士ともに免許資格なしです。
育休中に2020年後期保育士試験に挑戦し、現在結果待ちです。2021年1月半ば以降に結果が出ます。
もし今回の試験で保育士資格を取得できた場合、育休あけてから認定こども園で保育士として働かせていただけるとしても、幼稚園教諭取得の特例制度には当てはまることはできないでしょうか?
2025年の3月末までの延長となったと書かれていましたので、もしかしたら…と期待を持ったのですが。
もし特例制度にひっかかりそうでしたら、職場に、職種を変更してもらえないか相談し
てみようとおもいます。また特例制度の大学の受講を考えようと思います。
まだ保育士資格を取得できていないのに図々しい内容で大変申し訳ありません。
かよさん
コメントありがとうございます。
かよさんは、育休中に勉強をして、あの難しい保育士試験に挑戦しているのですね!
本当にすごい向上心です。
新しいことに挑戦したい!という思いを感じ、私も嬉しい思いがします。
では、かよさんのご質問にお答えする前に、ひとまず情報をまとめます。
かよさんは、
・私立の認定こども園で事務をされており、現在は育休中。
・育休の時間をつかって保育士試験を受験し、今は結果は待ち。
・仕事復帰は2021年9月。
・特例期間中に幼稚園教諭免許も取得したい。
という感じですね。
まず、結論からお伝えすると、
特例で幼稚園教諭免許を取得できる可能性があります!
具体的な数字で言うと、
2022年4月までに保育資格をもって【保育士】(フルタイム)として働きはじめれば、
2024年4月以降に【特例対象者】になります。
*ちなみに、幼保特例の対象者は【保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験のある方】です。
さらに具体的に書くと、
【保育士としてフルタイムで勤務した場合】
2022年4月~2023年3月→幼保特例の非対象
2023年4月~2024年3月→幼保特例の非対象
2024年4月~ →幼保特例の対象(2024年4月から2025年3月まで勤務する見込み)
という感じです。
ですので、あとは保育士試験の結果次第といったところでしょうか。
*注意*
上記の内容は私が個人的に調べてお伝えしていますので、公的な保証はありません。
(間違ってはないと思うのですが…)
ですので、必ずご自分で公的な機関に確認することを強くおすすめします。
*どこに確認したらいいか?*
それは、お住いの都道府県の教育委員会です。
*確認すべきこと*
・いつまでに保育士として働きはじめたら、2025年3月の幼保特例期間に間に合いますか?
・2022年4月から保育士として働いたら、2024年4月から幼保特例の対象者になりますか?
といった感じでしょうか。
以上、長くなってしまいましたが、私なりのお答えです。
子育てに、日々の生活。
そして、保育士試験から仕事復帰、保育士デビュー、保育士としての経験、幼保特例の挑戦。
やりがいのある毎日ですね!
陰ながら私も応援させてください。
何かあればいつでもまたご連絡くださいね(*^^*)
私も挑戦することが大好きで、このブログもその1つ。
少しずつですが、歩みを進めていこうと思っています。
お互いにがんばりたいですね!
それでは、また~。
早々にお返事感謝いたします。
また、希望のある内容にも感謝しかありません。
ご丁寧にありがとうございます。
もうひとつお伺いしたいです。
●もし今回、保育士資格を取得できた場合
●2022年4月までに認定こども園で保育士として働くことが可能となった場合。
上記2点がクリアされることが分かった場合、幼稚園教諭資格を取得するための特例制度の単位をとりに大学へ行けるのは、はやくていつからでしょうか?
保育士資格を取得できたら、すぐに行けるのであれば、育休中に単位取得をできたらなと考えています。
合格していないのに、またまた図々しい内容で申し訳ありません。笑
よろしくお願いいたします。
また教育委員会にも合格したら1度確認してみようとおもいます。
かよさん
ご質問ありがとうございます!
図々しいなんて思わなくて全然大丈夫ですよ。
成長したい、前に進みたいという思いの表れですよね。
私も挑戦することが大好きなので、
意欲にあふれたかよさんのことを応援したい気持ちでいっぱいです(*^^*)
さて、ご質問の件です。
保育士資格を取って2022年4月までに保育士として働き始めたとすると、
幼保特例で大学に行けるのは、最短で2024年の4月以降だと思います。
保育士として3年間働くというのが特例の条件ですが、
最後の1年間は「保育士3年間のみなし」で大学で勉強ができると私は認識しています。
こちらも、都道府県の教育委員会や日本福祉大学などに問い合わせて確認してくださいね。
ですので、ひとまずは保育士資格を取ることと、
保育士として働くことに全力を尽くすのが良いかと思います。
子育てをしながらなので思うようにいかないこともあるかもしれませんが、
子育てを楽しみつつ、ご自分のペースで前に進めるといいですね。
またいつでもコメントくださいね〜!
ありがとうございました。
ご丁寧に本当にありがとうございます。
よく分かりました。
今後もこちらのブログを参考にさせていただき、自分なりにぼちぼち進んでいきたいと思います。
特例制度を利用して幼稚園教諭二種免許を取るべく、日本福祉大学で単位を取りました。あとは教育委員会で手続きすれば免許状をもらえるんですよね?
ネットで見ていたら、単位を取り教育委員会に申請して教育職員検定を受けてくださいと書いてありました。試験を受けないといけないのですか?
あすかるさん、コメントありがとうございます!
返信遅くなりすみません。
ご質問ですが、結論から言いますと試験を受ける必要はありません。
申請をするだけですだから安心してください。
学力の証明や人物の証明、保育園で働いたと言う時間の証明等必要な書類を申請すれば大丈夫ですよ(^o^)
幼保特例の制度って本当にわかりにくいですよね〜。
こんばんわ!私は保育士免許を持っており今は育休中です!今年度から働いていた園がこども園になるという事で幼稚園教諭の免許を取らなくてはなりません。そこで質問なのですが、この日本福祉大学で取得できるのは幼稚園教諭第何種ですか?
かぶちゃんさん
コメントありがとうございます!
働いてる園がこども園に変わって幼稚園教諭の免許が必要になったとのこと。
新しい挑戦が始まりますね。
さて、質問への答えですが、結論から言うと
かぶちゃんさんの最終学歴によります。
・学士→1種
・高校卒→2種
という感じになります。
これは日本福祉大学だからではなく、どこで資格をとっても同じ結果となります。
以上、お答えでした〜。
また、なにかあればいつでもどうぞ(^o^)
読ませていただき勉強になりました!
あの相談です、、わたしは実習に行かなかっただけで幼稚園必修科目は在学中全てとりました。その場合どうしたらいいか市の幼保特例に問い合わせても分からないとの答えでした、、不安です、、どこに相談したらいいですか、、
tさん、コメントありがとうございます!
実習以外は全て科目を取り終えているのですね。
初めて聞く状況です。
結論から言うと、正直私にも何とも言えません。
ただ、確認すべきは以下の項目かと思います。
【確認先】
・お住まいの都道府県の教育委員会
【確認事項】
・実習以外の幼稚園教諭必修科目は取れている
・幼保特例と使用or不使用で、幼稚園免許を取る方法があるのかどうか?
以上をどうぞご確認ください。
そこまでいっていれば絶対に免許欲しいですよね!
何とかならないのかなと私もとても思います。
何か良い方法が見つかりますように!
教育委員会に電話するのは敷居が高く感じるかもしれませんが大事なことなのでぜひ電話で確認してみてください。
また何かありましたらいつでもご連絡くださいね(^o^)