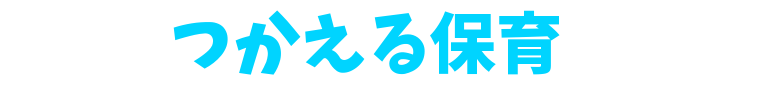ポイント
① “頭ではわかっているけどうまく伝えられない”をなくすために
② “ちゃんと伝えたのに伝わっていなかった”をなくすために
③ “どうやって伝えたらいいのかわからない”をなくすために
保育園や幼稚園で働いていると、“伝える”ということが山ほどありますが、
その“伝え方”を教えてもらうことは少ないように思います。
自分では“伝えた”と思ったけど、相手には“伝わってなかった”というようなことが、
私もよくありました。
自分の思いを相手に伝えることって、本当にむずかしいものですよね。
この記事では、“うまく伝わらない”を変えるための3つの方法を以下のようにまとめています。
① 情報を整理する
② 相手に“話を聞きたい”と思ってもらう
③ 信頼される伝え方を知る
どれも基本的なことですが、これらの技を覚えるだけで、ぐっと相手に伝わりますよ。
*保護者支援・対応の本をまとめた記事ができました。
全9冊をランキング形式で紹介しているので、保護者対応でお悩みの方はぜひご覧ください。
contents
情報を整理する(自分軸)

ポイント
① 頭の中の情報はまとまっているように見えてまとまっていない
② 保育現場は忙しいので、頭の中にはたくさんの情報がつまっている
自分で“わかっている”と思っても、誰かに説明するとうまく話せないことってありますよね。
それは、頭の中の情報はごちゃごちゃに混ざり合っており、きちんとまとまっていないからなのです。
この混ざり合った情報をどのようにしてきれいに整理すればいいのかをお伝えします。
紙に書き出す
頭の整理に1番いい方法は、紙に書き出すことです。
書き出せば情報は整理されますし、目で見える形になります。
ですので、会議などで伝える際にもポイントだけを伝えることができます。
面倒に感じるかもしれませんが、これが1番効果があることを覚えておいて下さい。
保育のスキル・伝え方の法則①
込み入ったことは、必ず書き出して整理しよう。
情報を“事実”と“推測”に分ける
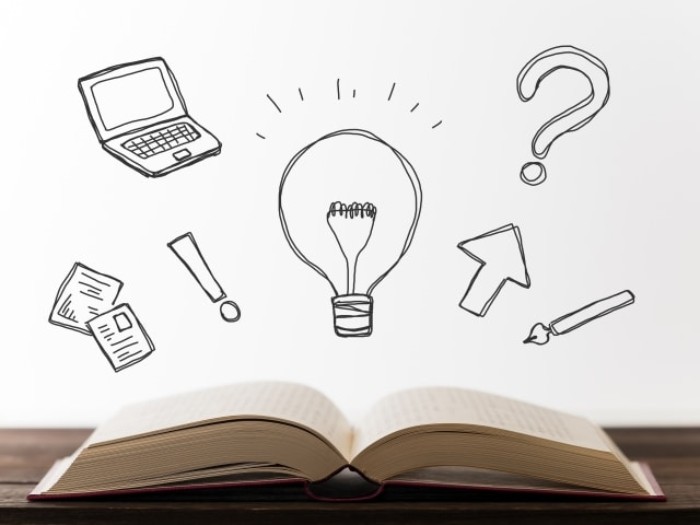
当たり前なことではありますが、とても大切です。
事実 → 自分が実際に見たり聞いたりしたこと
「~です」「~でした」と伝えます。
推測 → 部分的に見たり聞いたりしたこと
「~だと思います」「~のようです」と伝えます。
仕事や保育で求められるのは“事実”です。
事実をもとに、“次、どうしたらいいかな”と状況判断をして、仕事を進めていくからです。
推測がダメというわけではありません。
ただ、「私の感じたことや考えたことだから、本当かどうかはわからないのだ」と意識して相手に伝えなくてはいけません。
人に伝える前には、自分が持っている情報が“事実”なのか“推測”なのかを仕分けする習慣をつけてください。
保育のスキル・伝え方の法則②
“正しい情報”と“不確かな情報”を、区別しよう。
5W1Hをつかう【いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのようにして】

情報を“事実・推測”に仕分けするほかに、
“いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どうやって”と整理する方法もあります。
これを5W1Hといいます。
この5W1Hの流れに沿って考えることで、自分の頭の中が整理されますし、
人に伝える時にも、非常にわかりやすく伝えることができます。
不要かもしれませんが、実例をあげましょう。
例えば、
Aくんは 午前中に 庭で 転びました。
(誰が いつ どこで 何があったか)
手にボールを持って走っていたのでうまく手を着けず、左のほっぺを打ちました。
(なぜか 何があったか )
物を持って走ると危険なことを集まりで子どもたちに伝えて、同じような事故が続かないようにしています。
(どのようにして解決するか)
いつ、どこで、という順番はそのときの状況に応じて、話しやすい並びにしていいと思います。
大切なのは、5W1Hという情報の分け方を意識することです。
保育のスキル・伝え方の法則③
情報を5W1Hで整理しよう。
相手に“聞きたい”と思わせる(相手軸)

相手を不快にさせる話し方
① 話しのゴール(目的・結論)が見えない
② ゴールが見えても、内容がごちゃごちゃしている
③ 用件だけ伝える
自分の中の情報をいくら整理しても、伝え方がまずいと相手にストレスを与えてしまいます。
大事なのは、相手が“続きを聞きたい”と思うように話すことです。
具体的にいうと、
① 結論から言う
② 数字をつかって話す
③ クッション言葉をつかう
ということです。
本題に入る前に、これらの言葉を付け加えるだけで、
相手はあなたの話に興味を持ち、静かに耳をすませてくれると思います。
1つずつ説明していきます。
結論から言う

ポイント
結論を先に言うと、相手は安心して話を聞ける。
話の最初に、“結論”や“結果”、“どんな話をするのか”ということを一言で伝えることです。
そうすると、相手は“〇〇の話なんだな”と理解できるので、その後の話も安心して聞くことができます。
たとえば、職員会議で伝える場合。
・年長の遠足ですが、“○○公園”に行きたいと思います。(結論)
なぜなら・・・だからです。(理由)
・結果から言うと、中止になりました。(結果)
なぜなら・・・だからです。(理由)
・これから、○○さんからの~というクレームについてお伝えします。(何についての話か)
人前で話すとどうしても緊張やあせりが出て、話が長くなりやすいです。
また、否定されるのが怖くて、なぜ自分の話が正しいのか長々と説明してからやっと結論にたどり着くこともあるでしょう。
聞いている人にとってはストレスですし、「だから何なの?」とイライラしてしまいます。
だから、まず結論。
相手に話の見通しを持ってもらいましょう。
その後に、理由や状況などの説明。
相手に納得してもらいましょう。
保護者に子どものことを話す具体例も1つあげましょう。
事例が噛みつきなので、結論から言うという伝え方だけでなく、謝罪のやり方も合わせて説明します。
これは、子どもが友だちを噛んでしまった場合で、初めての噛みつきではないという状況です。
① おかえりなさい。(あいさつ)
② すみませんお母さん、今日○○くん、友だちを噛んでしまいました。
ちょっとそのことでお伝えをさせてください。(結果)
③ まずは、防ぐことができずに、申し訳ありませんでした。(謝罪)
④ 状況をお伝えしますと、~ということでした。(説明)
⑤ これから~という場面では特に気をつけてみていきます。(対策)
⑥ 本当に申し訳ありませんでした。(最後の謝罪)
私は、子どものけんかやケガなどを保護者に話す時、“結果”と“謝罪”を冒頭で伝えています。
いきなり“噛みつき”や“ケガ”の話をすると保護者もびっくりされますが、
その後の謝罪や説明、今後の対策などを聞く中で、保護者は少しずつ落ち着いていきます。
そして、状況がわかったうえで改めて謝罪を行うと、たいていの保護者は受け入れてくれます。
ただ、これが正解で、誰にでも、どんな状況でもOK!というわけではありませんのでお気をつけくださいね。
1つの事例として、参考にしてください。
保育のスキル・伝え方の法則④
結果をシンプルに、1番最初に伝えよう。
数字をつかって話す

ポイント
数字をつかうと、相手の頭に受け皿ができる。
最初に、話の全体像を数字で伝えるやり方です。
具体例をあげます。
・1年間の保育で大切にしたいことは3つあります。
・今回の誤食の原因は、大きく分けて3つあります。
このように、話の見通しを数字で示しています。
これも“結論から話す”と同じように、
相手に見通しを持ってもらい、安心して聞いてもらうためのテクニックです。
なお、例文は両方とも“3つあります”となっていますが、
“3”という数字は、1番伝わりやすい数字だと思います。
どうしても4つあるならば仕方ないですが、
5つや6つなど多くなってしまうと、相手も内容を覚えきれません。
3つというのが、相手の集中を切らさずに納得してもらう最適な数字ではないでしょうか。
保育のスキル・伝え方の法則⑤
話のポイントは3つにしよう。
クッション言葉をつかう

ポイント
クッション言葉がつかえると、お互いに気持ちいい。
言葉はストレートに伝えると、その衝撃はけっこう大きいものです。
家族ならいざ知らず、職場の人間関係において、
「これ、コピーして下さい」
「ここは、~ということですか?」などと、
いきなり用件だけを伝えると、相手はショックが大きいのではないでしょうか。
だから、
「お忙しいところ申し訳ないのですが、これを、コピーしてもらってもいいですか?」
「お仕事中すみません。1つだけお聞きしたいのですが、これは~ということでよかったでしょうか?」などと、
社会人は、相手の気持ちや状況を気づかう言葉を付け加えます。
これがクッション言葉です。
自分の思いだけを伝える一方的な関係ではなく、
相手の気持ちや状況を気づかい、クッション言葉として伝え、
相手と人間的な、優しい関係を築くことがとても大切だと思います。
では、クッション言葉の具体例をあげましょう。
【質問するとき】
・お仕事中すみません。少し話しかけてもよろしいですか?
・今、質問してもいいですか?
・教えていただきたいことがあるのですが
【お願いするとき】
・お忙しいところ申し訳ないのですが、書類の確認をお願いします
・もしよろしければ、運動会の企画案を見ていただきたいのですが
・お手数ですが、印刷をお願いします
・差支えなければ、ご連絡先を教えていただけますか?
・恐れ入りますが、少々お待ちいただけますか?
【断るとき】
・申し訳ありませんが、欠席させていただきます
・せっかくなのですが、お断りさせていただきます
・とても心苦しいのですが、出席はいたしかねます
・あいにくですが、園長は不在です
【改善をうながすとき】
・うまく伝えられずにすみません、ご記入はこちらにお願いします
・説明不足ですみません、入場はあちらからになります
【自分の意見を言うとき】
・ご存じの方も多いと思いますが
(ひかえめに自分の意見を伝える)
・○○先生もおっしゃっていましたが、私も~のように思います
(相手を立てることができ、人の話をよく聞いている印象を伝えられる)
・○○先生がおっしゃっていることは確かにその通りだと思います
ただ、私は~という理由から~ではないかと思います
(反対意見をやわらかく伝える)
他にも色々とあるでしょうが、ひとまずこんなところです。
ただ、人といい関係をつくる上でとても重要なクッション言葉にも注意点があります。
それは、クッション言葉をマニュアル的、機械的に使用しないということです。
相手を思って発せられる言葉も、条件反射でただ言っているだけになってしまうと、
あなたの気持ちが伝わらないばかりでなく、不誠実さが伝わってしまいます。
職場の人に支えられているという感謝の気持ちや、
保護者を尊重する気持ちが育っていないと、
クッション言葉を適切につかうことは難しいように思います。
ただの“スキル”にしない努力が必要ですね。
保育のスキル・伝え方の法則⑥
相手への“気づかい”を言葉にしよう。
信頼される伝え方と4つのメリット

TanteTati / Pixabay
【報告・連絡・相談・確認】
① 仕事がスムーズに進む
② 信頼される
③ 自分の身を守る
④ 考え方を学ぶ
信頼される伝え方とは、
いわゆる、“ほう・れん・そう”に“かくにん”を加えたものです。
職員間で連携をとり、仕事を順調に進めることができます。
また、“あの人はしっかりしている”“仕事を安心して任せられる”と信頼してもらえます。
このような関係があれば、多少伝え方がうまくなくても、
“あの人がいうことだから”と、ちゃんと聞いてもらうこともできます。
ここで大切になのは、“報告・連絡・相談・確認”の使い方を知ることです。
それぞれ具体的に説明していきます。
【報告】仕事の進み具合や状況を先輩や上司に伝える
・月案は半分できており、今週中には全て終わる予定です
・クラス写真の集計をまとめましたが、○○くんのところが未提出です
【連絡】関係者に情報を伝える(意見や推測は入れず、事実のみを伝える)
・来月の園だよりの締め切りは20日です
・調理保育に必要なものはエプロンと三角巾とマスクです
【相談】判断に迷うときに行う
・○○くんのお母さんから午睡を短くしてほしいと言われたのですが、どうしたらいいでしょうか?
・クラスで噛みつきが続いているのですが、どう対応したらいいでしょうか?
*ただ答えを求めるだけでなく、“自分は~と思うが、どうでしょうか?”と自分の意見も盛り込めるのが理想。
【確認】先輩や上司などに事前に確かめてから仕事をする
・今年のクリスマス制作はツリーにしようと思うのですが、よろしいでしょうか?
・明日までにこの書類を仕上げればいいのですよね?
“相談”と“確認”は少し似ているのですが、
“相談”は答えを相手と一緒に考えること。
“確認”は答えは自分の中にあり、念のため相手にも確認することだと思います。
さて、“報告・連絡・相談・確認”のメリットですが、ほかにも2つほどあります。
① 自分を守る
“相談・確認”をすることで、仕事の意思決定に、先輩や上司を巻き込みます。
たとえ仕事がうまく進まなくても、先輩や上司も一緒になって決めたのですから、
「自分の指示が十分ではなかった」と思ってもらえます。
むずかしい仕事の場合は、必ず周囲を巻き込みましょう。
② 考え方を学ぶ
できる先輩ほど仕事を効率的に進める方法や要点をつかんでいます。
先輩や上司に“相談”して意見をもらう中で、そんな仕事の極意を吸収することができます。
メリットしかない“報告・連絡・相談・確認”。
ぜひ、意識してやってみてください。
保育のスキル・伝え方の法則⑦
“ほう・れん・そう・かく”をマスターしよう。
伝え方の法則のまとめ
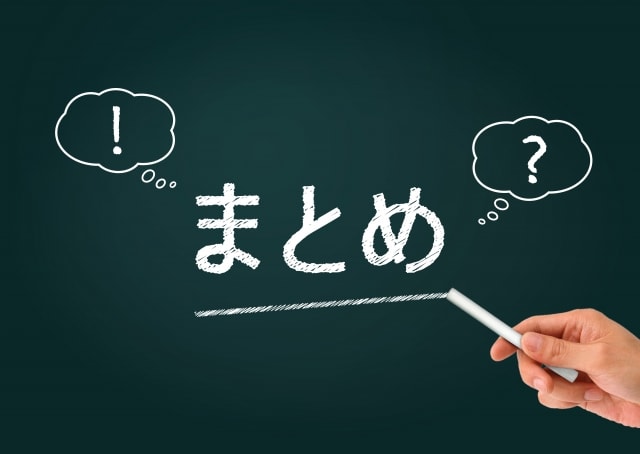
伝え方の法則
① 込み入ったことは、必ず書き出して整理しよう。
② “正しい情報”と“不確かな情報”を、区別しよう。
③ 情報を5W1Hで整理しよう。
④ 結果をシンプルに伝えよう。
⑤ 話のポイントは3つにしよう。
⑥ 相手への“気づかい”を言葉にしよう。
⑦ “ほう・れん・そう・かく”をマスターしよう。
相手に伝わるように話すには、まず情報の整理整頓が欠かせません。
その情報が事実なのか推測なのかを判断し、
“いつ・だれが・どこで・なにを・なぜ・どのようにしたのか”と情報を整理します。
そして、結論や数字、クッション言葉などをつかってシンプルに話し、
相手が気持ちよく話を聞けるような環境をつくります。
また、日ごろから“報告・連絡・相談・確認”を心がけ、
仕事をうまく進めるだけでなく、周囲の人たちと関係を築くことを大事にします。
そうすることで、話だけでなく、あなた自身のことも周囲の人にわかりやすく伝わり、
気づいた時には、周囲はあなたを応援してくれる人でいっぱいになっているはずです。
いきなり全部できなくても、1つずつ始めれば、物事はいい方向に動くと私は思います。
意識を変えて、行動に移してみてください。